カテゴリ「三国恋戦記」に属する投稿[45件](2ページ目)
『手に余る』 #仲花
合肥攻略の頃なので、仲花未満の関係性。仲謀視点。
『手繰った先にあるもの』の続きです。
****************
「それ、一緒に買ったやつ?」
急に真横から掛けられた声に、思わず器を落としそうになる。
「な、ん」
「あ、やっぱりそうだよね」
樽にたっぷりと溜まった水が、柄杓を入れられたことで大きく波立っている。ふと、腕にじとりと不快な感触を覚えて見遣れば、袖が濡れていた。器に入れたばかりの水を溢してしまったらしい。
「私もそれ待ってきたよ」
「……へえ」
「仲謀も使ってるんだ」
心なしか嬉しそうに聞こえるのは自分の願望だろうか。周囲の反対を押し切って合肥まで彼女を連れてきた。とはいえ軍議にもそうそう参加させるわけにもいかず、忙しい合間に見かける彼女はぷらぷらと暇そうにしていた。──即座に天幕で大人しくしていろと通達したはずだが。
「……お前こんなとこで何やってんだよ」
「お水飲もうと思って」
よくよく見れば、彼女も同じ紅い器を手にしている。思わず周囲の様子を窺うが、誰もこちらには注目していないようだった。ほっと胸を撫で下ろして、いや別に見られたところで何も悪いことはない、と頭を振った。
「前のも壊れてないから勿体ないんだけど、やっぱりこっちの方が好きなんだ」
「……そうかよ」
仄かに滲む喜色。手にしたままだった柄杓でもう一度水を汲み上げる。ゆらゆらと形を変え続ける水面を見ながら、花に器を出すよう顎で指図する。当然のように受ける彼女の姿に、少し前まで二人きりで旅をしていた時のことが鮮明に思い出された。とにかく、とにかく腹が立って仕方がない女だったはずなのに――。
「ありがとう」
何のてらいもなく、笑顔で礼を言われて思わず目を逸らす。最初に、この器を買った時に同じ言葉を言わせた。あの時の表情と比べれば、確実に関係も良くなってきているはずだ。
けれど。彼女のことを意識して見れば見るほど、誰にでも愛想良く笑顔を見せていることに気がついた。自分だけが特別ではない。出会った頃とは別の苛立ちに度々支配されるのを感じる。
内心舌打ちしながら、自分の器にも水を注ぎ入れる。
「なんか、一緒のって嬉しいね」
不意打ちのような言葉に、また水を溢しそうになる。
それは、どういう意味だろうか。少しぐらい、他の奴らよりも自分は彼女にとって特別だと思ってもいいのだろうか。
聞きたいのに、聞けない。一歩踏み出せば、望むものが手に入るかもしれない期待と、横にいることすら叶わなくなる可能性にたたらを踏む。
そうか。俺は怖いのか。
すとんと降りてきた思考に納得し、けれども向かい合いたくなくて、誤魔化すように器の中の水を一気に飲み干した。
「危ねえから天幕の中にいろよ」
「ちゃんといたよ」
不満そうに漏らす彼女を正面から見ることも出来ない。近くにいて欲しいと思うのに、いると酷く落ち着かない。居心地が悪い。
――本当に腹立たしい。
「いいか、余計なことに首突っ込むなよ。天幕の中で大人しくしてろ」
「……何で連れてきたの」
何故。そんなの、自分が知りたい。
「役に立つと思ったからだよ」
彼女は"軍師"としてここについてきた。それ以上でも以下でもない。わかっている。この器を求めた時だって、何の意味もなかったことぐらい、わかっているのだ。――だから、苛々する。
「……軍議にも出れないのに?」
「それでも必要だから連れてきたんだよ」
懐から布を取り出し器の水滴を拭う。そのままくるんで定位置に収めたところで、花がぽつりと言葉を零した。
「仲謀は――」
花が何かを言いかけて、止める。
「んだよ」
「……何でもない」
伏せた目からは何も読み取れない。ただ、彼女が楽しそうではないことだけはわかる。
何でもない顔ではないのに。こうやって自分に対して言えない何かを感じるのは、初めてではなかった。それが、気に入らないけれど、踏み込めない。──いや、踏み込みたいのだろうか。そしてどうするのだろう。こんなところまで連れてきて、玄徳軍に帰りたいという彼女を引き止めて、自分は何をしたいのだろう。
ああ、濡れた袖が気持ち悪い。
合肥攻略の頃なので、仲花未満の関係性。仲謀視点。
『手繰った先にあるもの』の続きです。
****************
「それ、一緒に買ったやつ?」
急に真横から掛けられた声に、思わず器を落としそうになる。
「な、ん」
「あ、やっぱりそうだよね」
樽にたっぷりと溜まった水が、柄杓を入れられたことで大きく波立っている。ふと、腕にじとりと不快な感触を覚えて見遣れば、袖が濡れていた。器に入れたばかりの水を溢してしまったらしい。
「私もそれ待ってきたよ」
「……へえ」
「仲謀も使ってるんだ」
心なしか嬉しそうに聞こえるのは自分の願望だろうか。周囲の反対を押し切って合肥まで彼女を連れてきた。とはいえ軍議にもそうそう参加させるわけにもいかず、忙しい合間に見かける彼女はぷらぷらと暇そうにしていた。──即座に天幕で大人しくしていろと通達したはずだが。
「……お前こんなとこで何やってんだよ」
「お水飲もうと思って」
よくよく見れば、彼女も同じ紅い器を手にしている。思わず周囲の様子を窺うが、誰もこちらには注目していないようだった。ほっと胸を撫で下ろして、いや別に見られたところで何も悪いことはない、と頭を振った。
「前のも壊れてないから勿体ないんだけど、やっぱりこっちの方が好きなんだ」
「……そうかよ」
仄かに滲む喜色。手にしたままだった柄杓でもう一度水を汲み上げる。ゆらゆらと形を変え続ける水面を見ながら、花に器を出すよう顎で指図する。当然のように受ける彼女の姿に、少し前まで二人きりで旅をしていた時のことが鮮明に思い出された。とにかく、とにかく腹が立って仕方がない女だったはずなのに――。
「ありがとう」
何のてらいもなく、笑顔で礼を言われて思わず目を逸らす。最初に、この器を買った時に同じ言葉を言わせた。あの時の表情と比べれば、確実に関係も良くなってきているはずだ。
けれど。彼女のことを意識して見れば見るほど、誰にでも愛想良く笑顔を見せていることに気がついた。自分だけが特別ではない。出会った頃とは別の苛立ちに度々支配されるのを感じる。
内心舌打ちしながら、自分の器にも水を注ぎ入れる。
「なんか、一緒のって嬉しいね」
不意打ちのような言葉に、また水を溢しそうになる。
それは、どういう意味だろうか。少しぐらい、他の奴らよりも自分は彼女にとって特別だと思ってもいいのだろうか。
聞きたいのに、聞けない。一歩踏み出せば、望むものが手に入るかもしれない期待と、横にいることすら叶わなくなる可能性にたたらを踏む。
そうか。俺は怖いのか。
すとんと降りてきた思考に納得し、けれども向かい合いたくなくて、誤魔化すように器の中の水を一気に飲み干した。
「危ねえから天幕の中にいろよ」
「ちゃんといたよ」
不満そうに漏らす彼女を正面から見ることも出来ない。近くにいて欲しいと思うのに、いると酷く落ち着かない。居心地が悪い。
――本当に腹立たしい。
「いいか、余計なことに首突っ込むなよ。天幕の中で大人しくしてろ」
「……何で連れてきたの」
何故。そんなの、自分が知りたい。
「役に立つと思ったからだよ」
彼女は"軍師"としてここについてきた。それ以上でも以下でもない。わかっている。この器を求めた時だって、何の意味もなかったことぐらい、わかっているのだ。――だから、苛々する。
「……軍議にも出れないのに?」
「それでも必要だから連れてきたんだよ」
懐から布を取り出し器の水滴を拭う。そのままくるんで定位置に収めたところで、花がぽつりと言葉を零した。
「仲謀は――」
花が何かを言いかけて、止める。
「んだよ」
「……何でもない」
伏せた目からは何も読み取れない。ただ、彼女が楽しそうではないことだけはわかる。
何でもない顔ではないのに。こうやって自分に対して言えない何かを感じるのは、初めてではなかった。それが、気に入らないけれど、踏み込めない。──いや、踏み込みたいのだろうか。そしてどうするのだろう。こんなところまで連れてきて、玄徳軍に帰りたいという彼女を引き止めて、自分は何をしたいのだろう。
ああ、濡れた袖が気持ち悪い。
『かんたんなこと』 #仲花
「三国恋戦記深夜の真剣お絵描き60分一本勝負」に参加で書きました(実際には1時間半)。
お題は「甘える/甘やかす」。
夫婦後のお話です。お題両方の意味をこめて全力で甘々に振り切りました(個人的に)。
****************
「正直、"甘える"とか不得意分野だよね」
ずばりと断言されて、お茶が変なところに入ってむせてしまう。
「だよねえ」
「まあ、花ちゃんにだけ言っても仕方ないんだけどさ」
「似たもの大婦だからねえ」
咳き込む私を気にも留めず、ため息をつく二人を涙目で見遣る。
「な、そんなこと、ないですよっ」
「え、じゃあ出来るの?」
全く期待していない双眸二つに見られて、ぐっと息が詰まった。
「……で、出来ないかどうかはやってみないと」
「やったことないんだよね」
「知ってたけどね」
「……」
長関な午後の昼下がり、おいしいお茶にお菓子。友人との楽しい語らいの時だ──のはずが、今日は少し勝手が違っていた。それもこれも、夫である仲謀のせいだった。
婚儀をあげ晴れて夫婦になってから数週間。元々忙しい人ではあったけれど、近頃は以前とは比べものにならない状態になっていた。なんやかやと開かれていた宴もめっきり減った。荊州のことを含め、次から次
へと難題が絶えないらしいと聞いている。
問題は、多忙を極めるがゆえに、仲謀の機嫌が悪いということだった。
「だ、大体、仲謀の機嫌が悪いのと、私に何の関係が」
「ないと思うの?」
「仲謀かわいそー」
「……私のせいで機嫌が悪いわけじゃないんですけど」
忙しさをどうすることもできない。
気晴らしである宴を開く暇すらない。
そこで自羽の矢が立ったのが私だった。
『甘えられると殿方は喜ぶものですよ』『いや奥方様が一言声をかけてくだされば』『夫婦ですもの。夫を労うのも妻の役日』とか何とか、会う人会う人に遠まわしに『仲謀を何とかしろ』と言われ辟易していた。
大喬さんと小喬さんならわかってくれるだろう、と愚痴をこぼしたところ、カウンターを食らってしまった。
「そりゃ花ちゃんのせいじゃないよ? でも仲謀のご機嫌をとれるのは花ちゃんだけなんだってば」
「どれだけ愛されてるのか自覚がないからなあ」
「「かわいそー」」
――だからそれと私が仲謀に甘えることに、何の関係があるのだろうか。
結局、楽しみにしていたお茶会をどんよりとした気持ちで終えることになった。嘘かに仲謀が疲れているのも苛ついているのも、何とかしてあげられたらとは思うけれど。
「……甘える、かあ」
昼間二人に言われた通り、やったこともなければ、何をすればいいのか検討もつかない。不得意、と言われた言葉がぐざりと刺さったままだ。
ふと、隣の部屋から声が漏れ聞こえ、戸が開いた。
「あれ、仲謀」
まだ夕餉の時間ですらない。こんな時間に自室に訪れることが稀で、目を瞬かせる。
「何か忘れ物?」
「少し休む」
短くそれだけを答えて、長椅子にさっさと座ってしまった。何かを考え込んでいるようで、目線は遠く険しい。……こういう時、部屋が同じだとどうしたらいいのか迷う。一人で考えたいからここに来たのではな
いか。邪魔ではないだろうか。
居心地の悪さを感じながら、おずおずと声をかけた。
「……。お茶、飲む?」
「いい」
即答だった。そんな言い方しなくても……。
昼間のこともあり、ここ最近の不満がもくもくと形を成していく。
大体、私には『抱え込むな』と言ったこともあるくせに、と腹が立ってきた。自分だって私には何も言おうとしてくれないのに──。
短く息を吸い、立ちあがる。そのままの勢いで、仲謀の横に腰かけた。彼が不思議そうにこちらを見たところで、睨み上げるように視線を合わせる。
「ねえ、私に甘えてほしいと思う?」
「……はあ?」
わからなければ、聞くしかない。急な話に、仲謀は呆れたような声を出した。
「そもそも、甘えるって何、どうやったらいいの?」
「な、何だよ急に。すげえ顧怖いぞお前」
「真剣に悩んでるの!」
思わず声を荒げると、仲謀が目を丸くして驚く。そして、ため息をついた。
「……何でそんな話に」
「仲謀が疲れてるみたいだから、みんなから甘えて癒してやったらどうとか言われて――」
「……」
私だって、出来るものならしてあげたいと思う。でも、私が甘えることが、何の意味があるのだろうという思いが消えない。
だって、問題とは関係のないことで、ただ誤魔化しているようにしか思えないのだ。それは仲謀にとって
失礼なんじゃないのか。
「……で、お前は納得してないんだろ」
心の内を読まれたような言葉に、驚いて顔を上げる。
途端、額に痛みが走った。
「いったああ」
「俺だって、そんなんで甘えられたって嬉しくねーんだよ
仲謀の指で弾かれた額を抑え、彼を仰ぎ見る。
「⋯⋯⋯そうなの?」
「お前が甘えたいからじゃないと、意味ないだろうが」
「……」
呆れたように、でも声音はすごく優しくて。胸が痛くなって、息が詰まる。
どうして、この人は。
肝心な時には必ず、欲しい言葉をくれるのだろう。
「……ていうか、悪かったな。俺がしっかりしてないからそんな―」
「ねえ」
「あ?」
「甘えてもいい?」
「だから――」
「私が、したいの」
するりと、自然に言葉が出た。仲謀の目が大きく見開かれて、泳いで、そして逸らされた。
「……そういうのは、訊かないでやれよ」
そう言いながら片手で顔を覆ったけれど、赤い耳が丸見えで。思わず口元が緩んだ。
どうしたらいいかわからないなんて、今となってみれば馬鹿馬鹿しいとさえ思うほど、ごく当たり前に身体が動いた。
隣に寄り添うように座りなおして、仲謀の肩に頭を預ける。くっついた場所からじわりと体温が伝わって、色んなものがゆっくり解けていくようだった。
「なんか、落ち若く」
「……そうかよ」
そっけないのに照れているのがよくわかる返事に、くすりと笑いが零れた。ああ、こんな風に笑ったのはいつぶりだろう。ただ隣にいて少し触れるだけでこんな気持ちになれるなら、早くそうすれば良かった。
思ったよりも、仲謀の不機嫌さに参っていたのは私だったのかもしれないと、今更そんなことに気が付く。
大好きな人が苦しそうなのは、私も辛い。何もできないもどかしさで、身動きがとれなくなっていたのだと、今ならわかる。
「ふふ。私が元気になっても仕方ないね」
「……じゃあ」
突如、言葉とともに腕を引かれる。気が付いたら、正面から抱きしめられていた。
「俺も甘えさせろ」
耳元で、いつもより低い仲謀の声が響く。
背中に回された仲謀の腕が熱くて、頬に触れる柔らかい髪がくすぐったくて。絶対に聞こえているであろう心臓の音を誤魔化したくて、とりあえず言葉を紡いだ。
「……甘えられるのって恥ずかしいね」
「知るか」
一際強く抱きしめられて、肩口に顔を埋められた。
あまりにも心臓が早く鳴りすぎているせいなのか、指先まで痛い。
「……元気、出そう?」
「ん」
短い、短いその言葉に胸をかき乱されながら、そっと仲謀の背中に手を回した。
今こうして触れているだけで満たされることがわかるから。仲謀が同じように感じていてくれることが嬉しくて、胸がいっぱいでどうしようもなくて、ただ静かに息を吐いた。
「三国恋戦記深夜の真剣お絵描き60分一本勝負」に参加で書きました(実際には1時間半)。
お題は「甘える/甘やかす」。
夫婦後のお話です。お題両方の意味をこめて全力で甘々に振り切りました(個人的に)。
****************
「正直、"甘える"とか不得意分野だよね」
ずばりと断言されて、お茶が変なところに入ってむせてしまう。
「だよねえ」
「まあ、花ちゃんにだけ言っても仕方ないんだけどさ」
「似たもの大婦だからねえ」
咳き込む私を気にも留めず、ため息をつく二人を涙目で見遣る。
「な、そんなこと、ないですよっ」
「え、じゃあ出来るの?」
全く期待していない双眸二つに見られて、ぐっと息が詰まった。
「……で、出来ないかどうかはやってみないと」
「やったことないんだよね」
「知ってたけどね」
「……」
長関な午後の昼下がり、おいしいお茶にお菓子。友人との楽しい語らいの時だ──のはずが、今日は少し勝手が違っていた。それもこれも、夫である仲謀のせいだった。
婚儀をあげ晴れて夫婦になってから数週間。元々忙しい人ではあったけれど、近頃は以前とは比べものにならない状態になっていた。なんやかやと開かれていた宴もめっきり減った。荊州のことを含め、次から次
へと難題が絶えないらしいと聞いている。
問題は、多忙を極めるがゆえに、仲謀の機嫌が悪いということだった。
「だ、大体、仲謀の機嫌が悪いのと、私に何の関係が」
「ないと思うの?」
「仲謀かわいそー」
「……私のせいで機嫌が悪いわけじゃないんですけど」
忙しさをどうすることもできない。
気晴らしである宴を開く暇すらない。
そこで自羽の矢が立ったのが私だった。
『甘えられると殿方は喜ぶものですよ』『いや奥方様が一言声をかけてくだされば』『夫婦ですもの。夫を労うのも妻の役日』とか何とか、会う人会う人に遠まわしに『仲謀を何とかしろ』と言われ辟易していた。
大喬さんと小喬さんならわかってくれるだろう、と愚痴をこぼしたところ、カウンターを食らってしまった。
「そりゃ花ちゃんのせいじゃないよ? でも仲謀のご機嫌をとれるのは花ちゃんだけなんだってば」
「どれだけ愛されてるのか自覚がないからなあ」
「「かわいそー」」
――だからそれと私が仲謀に甘えることに、何の関係があるのだろうか。
結局、楽しみにしていたお茶会をどんよりとした気持ちで終えることになった。嘘かに仲謀が疲れているのも苛ついているのも、何とかしてあげられたらとは思うけれど。
「……甘える、かあ」
昼間二人に言われた通り、やったこともなければ、何をすればいいのか検討もつかない。不得意、と言われた言葉がぐざりと刺さったままだ。
ふと、隣の部屋から声が漏れ聞こえ、戸が開いた。
「あれ、仲謀」
まだ夕餉の時間ですらない。こんな時間に自室に訪れることが稀で、目を瞬かせる。
「何か忘れ物?」
「少し休む」
短くそれだけを答えて、長椅子にさっさと座ってしまった。何かを考え込んでいるようで、目線は遠く険しい。……こういう時、部屋が同じだとどうしたらいいのか迷う。一人で考えたいからここに来たのではな
いか。邪魔ではないだろうか。
居心地の悪さを感じながら、おずおずと声をかけた。
「……。お茶、飲む?」
「いい」
即答だった。そんな言い方しなくても……。
昼間のこともあり、ここ最近の不満がもくもくと形を成していく。
大体、私には『抱え込むな』と言ったこともあるくせに、と腹が立ってきた。自分だって私には何も言おうとしてくれないのに──。
短く息を吸い、立ちあがる。そのままの勢いで、仲謀の横に腰かけた。彼が不思議そうにこちらを見たところで、睨み上げるように視線を合わせる。
「ねえ、私に甘えてほしいと思う?」
「……はあ?」
わからなければ、聞くしかない。急な話に、仲謀は呆れたような声を出した。
「そもそも、甘えるって何、どうやったらいいの?」
「な、何だよ急に。すげえ顧怖いぞお前」
「真剣に悩んでるの!」
思わず声を荒げると、仲謀が目を丸くして驚く。そして、ため息をついた。
「……何でそんな話に」
「仲謀が疲れてるみたいだから、みんなから甘えて癒してやったらどうとか言われて――」
「……」
私だって、出来るものならしてあげたいと思う。でも、私が甘えることが、何の意味があるのだろうという思いが消えない。
だって、問題とは関係のないことで、ただ誤魔化しているようにしか思えないのだ。それは仲謀にとって
失礼なんじゃないのか。
「……で、お前は納得してないんだろ」
心の内を読まれたような言葉に、驚いて顔を上げる。
途端、額に痛みが走った。
「いったああ」
「俺だって、そんなんで甘えられたって嬉しくねーんだよ
仲謀の指で弾かれた額を抑え、彼を仰ぎ見る。
「⋯⋯⋯そうなの?」
「お前が甘えたいからじゃないと、意味ないだろうが」
「……」
呆れたように、でも声音はすごく優しくて。胸が痛くなって、息が詰まる。
どうして、この人は。
肝心な時には必ず、欲しい言葉をくれるのだろう。
「……ていうか、悪かったな。俺がしっかりしてないからそんな―」
「ねえ」
「あ?」
「甘えてもいい?」
「だから――」
「私が、したいの」
するりと、自然に言葉が出た。仲謀の目が大きく見開かれて、泳いで、そして逸らされた。
「……そういうのは、訊かないでやれよ」
そう言いながら片手で顔を覆ったけれど、赤い耳が丸見えで。思わず口元が緩んだ。
どうしたらいいかわからないなんて、今となってみれば馬鹿馬鹿しいとさえ思うほど、ごく当たり前に身体が動いた。
隣に寄り添うように座りなおして、仲謀の肩に頭を預ける。くっついた場所からじわりと体温が伝わって、色んなものがゆっくり解けていくようだった。
「なんか、落ち若く」
「……そうかよ」
そっけないのに照れているのがよくわかる返事に、くすりと笑いが零れた。ああ、こんな風に笑ったのはいつぶりだろう。ただ隣にいて少し触れるだけでこんな気持ちになれるなら、早くそうすれば良かった。
思ったよりも、仲謀の不機嫌さに参っていたのは私だったのかもしれないと、今更そんなことに気が付く。
大好きな人が苦しそうなのは、私も辛い。何もできないもどかしさで、身動きがとれなくなっていたのだと、今ならわかる。
「ふふ。私が元気になっても仕方ないね」
「……じゃあ」
突如、言葉とともに腕を引かれる。気が付いたら、正面から抱きしめられていた。
「俺も甘えさせろ」
耳元で、いつもより低い仲謀の声が響く。
背中に回された仲謀の腕が熱くて、頬に触れる柔らかい髪がくすぐったくて。絶対に聞こえているであろう心臓の音を誤魔化したくて、とりあえず言葉を紡いだ。
「……甘えられるのって恥ずかしいね」
「知るか」
一際強く抱きしめられて、肩口に顔を埋められた。
あまりにも心臓が早く鳴りすぎているせいなのか、指先まで痛い。
「……元気、出そう?」
「ん」
短い、短いその言葉に胸をかき乱されながら、そっと仲謀の背中に手を回した。
今こうして触れているだけで満たされることがわかるから。仲謀が同じように感じていてくれることが嬉しくて、胸がいっぱいでどうしようもなくて、ただ静かに息を吐いた。
『遠い空の下』 #仲花
エンド後、尚香さんが玄徳軍に行った仮定のお話。
****************
思うように動かない指先と、期待に反してぽきりと折れてしまう茎。首を傾げながら、ちぐはぐに連なった花輪のできそこないを、頭上に掲げた。
「いけると思ったんだけどなあ」
「何やってんだよ」
草むらに座り込んだ私を呆れた目で見降ろす仲謀の言葉に、腕をそっと下ろした。
「⋯⋯花冠か」
「うん」
城内の塀に近い、草が生い茂っている場所で、シロツメクサによく似た花を見つけた。
死角の人気のない場所だったものだから、座り込み記憶を頼りに花冠作りに勤しんでい
た。しかし、編み込む過程で茎は萎れ、花の位置もまばらで全くうまくできない。
「ちょっと貸せ」
顎で示され、どうするんだろうと訝しみながらも、花冠のできそこないを渡す。しゃがんだ仲謀の骨ばった手が花を摘み、私が作ったものに差し込むまでの流れが至って白然で、思わず目を瞬かせた。
あっという間に、まばらに並んだ花がみっしりと連なっていく。
「⋯⋯作ったことあるの?」
「尚否に強諦られて」
あいつ不器用だろ。そう言いながら口端をあげた仲謀の横顔は、どこか寂し気だった。
尚香さんと入れ替わるように、京へと戻ってきた。
別れ際に「義姉上」と日を潤ませて手を繋いできた彼女を思い出す。 固い決意のもと玄徳軍に嫁いだとはいえ、本当に他に道はなかったのだろうか。
何度も繰り返した白問を、短く息を吐くことで終わらせる。ただ、私が寂しいのだ。そんなだから、仲謀の横顔が寂しそうだなんて、思いたいのかもしれない。
「ほら、できたぞ」
沈んだ思考の沼に浸かりかけたころ、目の前に輪になった花冠が差し出された。
「わあ、すごい。綺麗」
「別に。大したことないだろ」
と言いつつも、気をよくしたようで、仲謀が鼻を鳴らす。そして腰を下ろして伸びをしたかと思うと、そのまま寝転がった。
「ありがと」
「別に」
いつでも作ってやるよ、と続いた言葉が面映ゆい。と同時に、かつて尚香さんにも言っていたのは想像に難くない。きっと口では色々言いつつも、面倒見よく大事にしていただろう。――その尚香さんは、もういない。
春風が、そよそよと草花を揺らし通り抜けていく。遠くからは鍛錬の声や、人々が談笑する声が流れてくる。頭上には、柔らかく千切られた雲が点々と、透き通った水色の空に浮かんでいる。気持ちとは裏腹に、どこまでも穏やかな光景だ。
「女ってほんとそういうの好きだな」
「……可愛いじゃない」
尚呑さんのことを思い出しているのだろうか。嫁がせたことを、後悔しているのだろうか。たとえそうだったとして、仲謀は絶対に言わないだろう。
尚香さんがいなくて寂しいね。そう言いたいのに、話してもらえない現実を思うと、言う気にはなれなかった。
それは仲謀の立場を考えれば当然のことであることは理解している。でも、もしこれから夫婦になったとして。私は、仲謀にどれだけのことを打ち明けてもらえるのだろう。
手元の花冠を眺める。私が出来ないことは、仲謀が支えてくれるのかもしれない。
じゃあ、私は?もう本もない、軍師としてここにいるわけでもない。私が仲謀にできることって、何なんだろう。
「……」
手元の花冠を、そっと撫でた。
──私がこの人にあげられるものは、何にもない。
「仲謀」
「あ?」
そっと、仲謀の頭に花冠を乗せる。
「――何で俺に乗せるんだよ」
「……"ありがとう"の代理?」
ぽかん、と口を開けて仲謀がこちらを見上げる。そして、大きく破顔した。
「何だそれ」
私は何もあげられないし、尚香さんがいなくて寂しいね、と声をかける勇気だってないけれど。
貴方が今まで築いてきたものを、これから作り上げていくものを、貴方が気ものを見て伝えて。「いつでも」の言葉が叶うように、貴方の傍にいるよ。
エンド後、尚香さんが玄徳軍に行った仮定のお話。
****************
思うように動かない指先と、期待に反してぽきりと折れてしまう茎。首を傾げながら、ちぐはぐに連なった花輪のできそこないを、頭上に掲げた。
「いけると思ったんだけどなあ」
「何やってんだよ」
草むらに座り込んだ私を呆れた目で見降ろす仲謀の言葉に、腕をそっと下ろした。
「⋯⋯花冠か」
「うん」
城内の塀に近い、草が生い茂っている場所で、シロツメクサによく似た花を見つけた。
死角の人気のない場所だったものだから、座り込み記憶を頼りに花冠作りに勤しんでい
た。しかし、編み込む過程で茎は萎れ、花の位置もまばらで全くうまくできない。
「ちょっと貸せ」
顎で示され、どうするんだろうと訝しみながらも、花冠のできそこないを渡す。しゃがんだ仲謀の骨ばった手が花を摘み、私が作ったものに差し込むまでの流れが至って白然で、思わず目を瞬かせた。
あっという間に、まばらに並んだ花がみっしりと連なっていく。
「⋯⋯作ったことあるの?」
「尚否に強諦られて」
あいつ不器用だろ。そう言いながら口端をあげた仲謀の横顔は、どこか寂し気だった。
尚香さんと入れ替わるように、京へと戻ってきた。
別れ際に「義姉上」と日を潤ませて手を繋いできた彼女を思い出す。 固い決意のもと玄徳軍に嫁いだとはいえ、本当に他に道はなかったのだろうか。
何度も繰り返した白問を、短く息を吐くことで終わらせる。ただ、私が寂しいのだ。そんなだから、仲謀の横顔が寂しそうだなんて、思いたいのかもしれない。
「ほら、できたぞ」
沈んだ思考の沼に浸かりかけたころ、目の前に輪になった花冠が差し出された。
「わあ、すごい。綺麗」
「別に。大したことないだろ」
と言いつつも、気をよくしたようで、仲謀が鼻を鳴らす。そして腰を下ろして伸びをしたかと思うと、そのまま寝転がった。
「ありがと」
「別に」
いつでも作ってやるよ、と続いた言葉が面映ゆい。と同時に、かつて尚香さんにも言っていたのは想像に難くない。きっと口では色々言いつつも、面倒見よく大事にしていただろう。――その尚香さんは、もういない。
春風が、そよそよと草花を揺らし通り抜けていく。遠くからは鍛錬の声や、人々が談笑する声が流れてくる。頭上には、柔らかく千切られた雲が点々と、透き通った水色の空に浮かんでいる。気持ちとは裏腹に、どこまでも穏やかな光景だ。
「女ってほんとそういうの好きだな」
「……可愛いじゃない」
尚呑さんのことを思い出しているのだろうか。嫁がせたことを、後悔しているのだろうか。たとえそうだったとして、仲謀は絶対に言わないだろう。
尚香さんがいなくて寂しいね。そう言いたいのに、話してもらえない現実を思うと、言う気にはなれなかった。
それは仲謀の立場を考えれば当然のことであることは理解している。でも、もしこれから夫婦になったとして。私は、仲謀にどれだけのことを打ち明けてもらえるのだろう。
手元の花冠を眺める。私が出来ないことは、仲謀が支えてくれるのかもしれない。
じゃあ、私は?もう本もない、軍師としてここにいるわけでもない。私が仲謀にできることって、何なんだろう。
「……」
手元の花冠を、そっと撫でた。
──私がこの人にあげられるものは、何にもない。
「仲謀」
「あ?」
そっと、仲謀の頭に花冠を乗せる。
「――何で俺に乗せるんだよ」
「……"ありがとう"の代理?」
ぽかん、と口を開けて仲謀がこちらを見上げる。そして、大きく破顔した。
「何だそれ」
私は何もあげられないし、尚香さんがいなくて寂しいね、と声をかける勇気だってないけれど。
貴方が今まで築いてきたものを、これから作り上げていくものを、貴方が気ものを見て伝えて。「いつでも」の言葉が叶うように、貴方の傍にいるよ。
『手繰った先にあるもの』 #仲花
黄巾党の時代に飛ばされたばかりの頃のお話。
続きはこちら
****************
居心地が悪い。雑踏の中、ちらりと横にいる人物を盗み見た。色素の薄い髪が、陽光を受けて光りを散らす。女性とすれ違えばヒソヒソとはしゃいだ声がついてくる。そうなるのも納得するぐらい、不機嫌そうな顔つきは彼の魅力をよく惹き立てていた。
また、あの本によって過去に飛ばされたその日。今度は、たまたま居合わせた彼――孫仲謀――も一緒だ。一人きりよりはマシだけれど、あまり仲が良いとも言えない人が横にいるというのは、なんとも気まずい。
下山し、とりあえず目的地も決まったところで、今は入用の物を見繕っている最中だ。
「おい、ぼさっとしてんなよ」
少し馴染み始めた彼の苛立った声にこっそりため息をつきながら、早足で横に並ぶ。
「あと必要なものは――」
「「椀」とか?」
思わず被った声。じろりと彼がこちらを見た。言葉に詰まれば、鼻を鳴らしてそっぽを向く。――本当に感じ悪い人だな。
椀は川の水を飲むにも、街中で何かを買う際にも洗ったり拭いたりしては使い回しをする。行軍で知ったこの時代の習慣だ。玄徳軍で貰ったものは、京城であてがわれた客室に置かれたままだろう。
「あそこで揃えるか」
彼に倣って同じ方を見れば、路面に敷布を広げた雑貨屋のような露店があった。言うなりさっさと一人で向かった仲謀の後を、慌てて追いかける。
「おい、椀が欲しいんだが」
「はいはい。――っとそうですね、こちらはどうでしょう。お安くしときますよ」
店主はちらりとこちらを一瞥した後、椀を二つ差し出した。一目で揃いだと分かるそれらに、思わず気持ちが上がる。漆塗りのそれは、子どもの頃のままごとの椀を思いださせた。特に紅い色が良い。
「かわいい」
「……他にないのか」
「え、これでいいと思うけど。大きさも丁度良いよね」
仲謀の声は渋い。店主の提示する値段も悪くないと思うが、もう少し質が良いものを、ということだろうか。しかし、これまで買い揃えた物にそういう拘りを見せることはなかった。
仲謀の言葉に気を悪くすることもなく、店主のおじさんは籠の中からいくつか椀を取り出した。けれど――。
「……私、やっぱりこれがいいな」
「お、前なぁ」
何故か上擦った仲謀の声に疑問を挟む暇もなく、店主が畳み掛けてくる。
「いやぁ、中々揃いを求める人がいなくてね。もう少しまけてあげよう」
「本当ですか?」
ほら、やっぱりこれにしようと仰ぎみれば、見たことのない渋面。意味がわからず首を傾げた。――怒っているわけではなさそうだが。
「……わかったよ」
「いやあ、良い旦那さんだね」
「え、いや、あの」
「行くぞ」
さっさとお金を渡し、仲謀は先に立ち去ってしまった。慌てて追いかけて、財布代わりにしている巾着を取り出す。
「半分出すよ」
「いい」
言葉少なにこちらも見ずに、赤い器を一つ押しつけられる。
「……ごめん」
そんなにこれが嫌だったのだろうか。色が嫌いとか? 手元の椀を心許ない気持ちで眺める。さっきまでの浮きたった心はどこかに消えてしまった。
「あのなあ」
急に足を止めた仲謀が、頭をがしがしと掻きながら、振り返らずに言葉を溢した。
「そう言う時はまず礼が先だろうが」
「……ありがとう」
“ひとまず”の礼に、彼は舌打ちした。機嫌は相変わらず悪い。ただ、今まではとは種類が違うように思えたが、それが何故なのかはわからない。
相手が何を考えているのか捉えられないことが、こんなにも足元をおぼつかなくさせるなんて。これまでの交友関係を思い出しながら、今後どう付き合っていくべきか頭を悩ませ――たところで話しかけられた。
「――気に入ってんだろ」
「へ?」
目を瞬かせて仲謀の顔を仰ぎ見る。相変わらず彼は向こうを向いたままだなので、表情まではわからない。
「なら、もっと嬉しそうにしとけよ」
――それはそれで文句言いそうなんだよなあ、この人。
自分の思いつきに、口端が自然と緩む。だって、その光景が目に浮かぶ。
「何笑ってんだよ」
「ふふふっ」
やっぱり。堪えきれずに笑いをこぼせば、ものすごく嫌そうな視線が向けられる。
「変なやつ」
それは仲謀の方なんじゃないかな、という言葉をかろうじて飲み込んで、歩き出した彼の後ろをついていった。
黄巾党の時代に飛ばされたばかりの頃のお話。
続きはこちら
****************
居心地が悪い。雑踏の中、ちらりと横にいる人物を盗み見た。色素の薄い髪が、陽光を受けて光りを散らす。女性とすれ違えばヒソヒソとはしゃいだ声がついてくる。そうなるのも納得するぐらい、不機嫌そうな顔つきは彼の魅力をよく惹き立てていた。
また、あの本によって過去に飛ばされたその日。今度は、たまたま居合わせた彼――孫仲謀――も一緒だ。一人きりよりはマシだけれど、あまり仲が良いとも言えない人が横にいるというのは、なんとも気まずい。
下山し、とりあえず目的地も決まったところで、今は入用の物を見繕っている最中だ。
「おい、ぼさっとしてんなよ」
少し馴染み始めた彼の苛立った声にこっそりため息をつきながら、早足で横に並ぶ。
「あと必要なものは――」
「「椀」とか?」
思わず被った声。じろりと彼がこちらを見た。言葉に詰まれば、鼻を鳴らしてそっぽを向く。――本当に感じ悪い人だな。
椀は川の水を飲むにも、街中で何かを買う際にも洗ったり拭いたりしては使い回しをする。行軍で知ったこの時代の習慣だ。玄徳軍で貰ったものは、京城であてがわれた客室に置かれたままだろう。
「あそこで揃えるか」
彼に倣って同じ方を見れば、路面に敷布を広げた雑貨屋のような露店があった。言うなりさっさと一人で向かった仲謀の後を、慌てて追いかける。
「おい、椀が欲しいんだが」
「はいはい。――っとそうですね、こちらはどうでしょう。お安くしときますよ」
店主はちらりとこちらを一瞥した後、椀を二つ差し出した。一目で揃いだと分かるそれらに、思わず気持ちが上がる。漆塗りのそれは、子どもの頃のままごとの椀を思いださせた。特に紅い色が良い。
「かわいい」
「……他にないのか」
「え、これでいいと思うけど。大きさも丁度良いよね」
仲謀の声は渋い。店主の提示する値段も悪くないと思うが、もう少し質が良いものを、ということだろうか。しかし、これまで買い揃えた物にそういう拘りを見せることはなかった。
仲謀の言葉に気を悪くすることもなく、店主のおじさんは籠の中からいくつか椀を取り出した。けれど――。
「……私、やっぱりこれがいいな」
「お、前なぁ」
何故か上擦った仲謀の声に疑問を挟む暇もなく、店主が畳み掛けてくる。
「いやぁ、中々揃いを求める人がいなくてね。もう少しまけてあげよう」
「本当ですか?」
ほら、やっぱりこれにしようと仰ぎみれば、見たことのない渋面。意味がわからず首を傾げた。――怒っているわけではなさそうだが。
「……わかったよ」
「いやあ、良い旦那さんだね」
「え、いや、あの」
「行くぞ」
さっさとお金を渡し、仲謀は先に立ち去ってしまった。慌てて追いかけて、財布代わりにしている巾着を取り出す。
「半分出すよ」
「いい」
言葉少なにこちらも見ずに、赤い器を一つ押しつけられる。
「……ごめん」
そんなにこれが嫌だったのだろうか。色が嫌いとか? 手元の椀を心許ない気持ちで眺める。さっきまでの浮きたった心はどこかに消えてしまった。
「あのなあ」
急に足を止めた仲謀が、頭をがしがしと掻きながら、振り返らずに言葉を溢した。
「そう言う時はまず礼が先だろうが」
「……ありがとう」
“ひとまず”の礼に、彼は舌打ちした。機嫌は相変わらず悪い。ただ、今まではとは種類が違うように思えたが、それが何故なのかはわからない。
相手が何を考えているのか捉えられないことが、こんなにも足元をおぼつかなくさせるなんて。これまでの交友関係を思い出しながら、今後どう付き合っていくべきか頭を悩ませ――たところで話しかけられた。
「――気に入ってんだろ」
「へ?」
目を瞬かせて仲謀の顔を仰ぎ見る。相変わらず彼は向こうを向いたままだなので、表情まではわからない。
「なら、もっと嬉しそうにしとけよ」
――それはそれで文句言いそうなんだよなあ、この人。
自分の思いつきに、口端が自然と緩む。だって、その光景が目に浮かぶ。
「何笑ってんだよ」
「ふふふっ」
やっぱり。堪えきれずに笑いをこぼせば、ものすごく嫌そうな視線が向けられる。
「変なやつ」
それは仲謀の方なんじゃないかな、という言葉をかろうじて飲み込んで、歩き出した彼の後ろをついていった。
『白線』 #仲花
2020/11/04→2021/01/02加筆修正
仲謀×花の甘くないお話。
続きのようなお話はこちら から。
****************
吐く息が白い。
ふと、教科書に載っていた氷の結晶の写真を思い出す。吐息があんな形になって落ちているような気がする。
「行くぞ」
ひそめた声に、手に息を吐きかけるのをやめて後ろをついていく。辺りは暗く、冷えた空気がぴたりと身体に張り付き、芯から熱を奪っていく。
「ねえ、どこに行くの」
昨日、陽が昇る前に出かけるから準備をしろと言われた。朝日の気配が微塵も感じられない今、いつもと印象の違う外套を着た彼が、約束通り迎えに来たところだ。季節は真冬。加えて熱源は己の身体のみ。いくら厚めの上着を着ていても、寒さで唇がわななく。
「ねえ」
「静かにしろ。見つかるだろうが」
ちっとも説明をする気のない背中を半眼で見つめ、相変わらず強引だなとため息をつく。空を見上げれば、ちらちらと星が静かに瞬いていた。きんと冷えた空気に、雪が降りそうだと思う。
静かな空間に二人の足音だけが落ちる中、裏門の近くに何かが見えた。同時に、動物の気配を感じ取る。馬だ。小さな嘶きと共に、足を軽く踏み鳴らしている。
「悪い。待たせたな」
何度か見かけたことのある年配の男性。確か厩番の人だ。「久々ですね」と呆れたように彼に笑いかけている。
「……馬に乗るの?」
「ああ」
こちらを見ることなく答えた彼は、あっという間に馬上の人となってしまう。そして私に向かって手を伸ばした。
「ほら」
こうして、何度も馬に乗ったのはいつだったか。この人が馬にだけは優しいと思ったこともあった。
硬い、私より大きな手を掴めば、あっという間に馬の上へと引き上げられる。彼の手は、熱かった。
「あまり遅くなりませぬよう……」
「わかってる。心配をかけない内に戻る」
「……それは無理ではないかと」
苦笑しながら拱手し頭を垂れた男性を横目に、手綱をしっかりと握らされた。
「ちゃんと握っとけよ」
「う、うん」
馬は何度乗っても慣れない。一人で乗れないからだろうか。どしりとした足元の馬の体幹と、背中の彼の気配で不安は感じないものの、生き物の上に跨るのは独特の緊張感がある。ぶるる、と馬が鼻を鳴らしながら首を振った。
「行くぞ」
ぐっと身体に力を込め最初の揺れに耐えてしまえば、重い振動も軽やかなリズムに飲み込まれ気にならなくなる。
寝静まった街の中を、馬はどんどん駆けていく。時折灯りと笑い声が響く店がある以外は、本当に静かだ。思えばこんな暗い時間に馬に乗るのは初めてで、前方がよく見えず不安になる。
「ねえ」
城を出たからいいだろう、と少し声を張り上げれば、「なんだ」と声が降ってきた。
「どこに行くの?」
「何でそんなに気にするんだよ」
「……普通するよ」
ぶつかってくる冬の冷たい空気に、露出した部分がちりちりと痛む。手綱を離すわけにもいかず、外套を上げることすら叶わない。これ以上聞く気もなくして、かじかむ手で手綱を離さぬよう、握りしめることに集中した。
そうこうしている内に、あっという間に門前まで辿り着いた。門番と二、三やりとりを交わし、馬の足音を響かせ街の城門を抜ける。街中ではないから灯りもない。かろうじて判別できるのは道ぐらいだ。その中をひたすらどこかへ向かって走っていく。本当にどこに行くつもりだろう、と思っていると彼が喋りはじめた。
「久々に時間が空いたからな。少し遠出するぞ」
「……内緒でお出かけなの?」
「まあな。昔はよくやってた」
彼が笑った気配がする。その顔を思い浮かべて、小さく笑みをこぼす。
ふいに、うっすらと暗闇が遠のき始めた。ぼんやり眺めていると、黒い山々の稜線に光が走る。それは数度瞬きする間にも色を変え続け、天地の境界をはっきりと染め上げていく。思わずため息がこぼれた。
馬の走る速度は落ちない。でもきっと彼もこの光景を見ているだろう。
「綺麗だね、──」
喉が張り付いていて、一瞬息ができなかった。
大きく喉を上下させ唾を飲み込み、ぱちぱちと瞬きを繰り返す。身体が、酷く冷えている。
自分の身体を見下ろせば、掛布団がベッドからずり落ちていた。それは寒いはずだ。風邪を引くかもしれない、とぼんやりした頭で思う。
身体を動かすのも億劫で、視線だけで辺りを見渡す。見慣れた天井、カーテン。外は次第に明るくなってきているらしく、部屋の中は容易に見渡せた。目覚まし時計に手を伸ばして確認すれば、日の出を少し過ぎた頃だ。
『綺麗だね、 』
また、あの人の夢を見た。
息を細く吐いて、力の入らない腕で何とか起き上がる。
カーテンを開けてみると、ちょうど建物との境目を滲ませながら、朝陽が昇っているところだった。溶けたオレンジ色が、徐々に丸く、そして見ることを拒絶するように光を強めていく。目を細めて逸らし、カーテンを閉じた。
今のより、綺麗な朝焼けだった。馬なんて一度も乗ったことがないのに、揺れる感触も、暖かな馬の胴体も、何故か知っているような気がする。
――あの人のことも、知っている。金色の髪。目の色は、青だったり灰色だったり、光の具合で違う。すぐ怒ったように話す。でも、優しい人だ。優しくて、強い人。
そこまで考えて、くすりと笑いがれこぼた。――夢なのに、『知ってる』なんて。けれども、確かめずにはいられなかった。
「……綺麗だね、」
自分が言った台詞を反芻してみても、確かに夢の中で呼びかけたはずの名前は出てこなかった。
息を吐く。今日は吐いた先から凍り付くように寒い。
首に巻いたマフラーを口元まであげれば、喉が少し痛いことに気が付いた。やはり風邪を引き始めている。
『体調悪いのか?いつからだ』
ふいに、あの人にかけられた言葉を思い出した。表情だって、思い出せる。今まで忘れていたというのに……。夢を見ると、こうして記憶になかったものが溢れることがある。
──ああ、駄目だ。今日は駄目な日だ。
唇を引き結ぶ。そうしなければ泣いてしまいそうだった。
名前も知らないあの人のことが、頭から離れない。話した記憶にない声が、頭の中を占めていく。
長く息を吐いて頭上を見上げれば、小さな白い欠片がふわふわと舞い降り始めていた。
──あの後、雪は降ったのだろうか。
舞い降りる雪は小さすぎて、触れるか触れないかの距離で消えてしまう。あの人のことも同じ。痕跡を探そうとすればするほど、輪郭がぼやけてしまう。今頭の中を占めている声も、表情も。夢を見るたびに思い出しては消えていくのだ。
具体的なことは何一つ残ってくれないのに、あの人への気持ちだけが結晶みたいに綺麗に整えられていく。
堪えきれなくなった雫が、熱く頬を滑り落ちていく。
でも、覚えていたいわけではないのだ。だって、必要がない。他愛なく交わした言葉も。隠し事ができないから、すぐに変わる表情も。自分よりも他を優先する強さからくる優しさも――。『選ばなかった』私には、全部、全部、必要のないものだ。どうせ、これもすぐに忘れてしまう。
『誰』とか、そんなのどうでもいい。
あなた以上に好きだと思える人がいないことだけを、私は覚えていればいい。
2020/11/04→2021/01/02加筆修正
仲謀×花の甘くないお話。
続きのようなお話はこちら から。
****************
吐く息が白い。
ふと、教科書に載っていた氷の結晶の写真を思い出す。吐息があんな形になって落ちているような気がする。
「行くぞ」
ひそめた声に、手に息を吐きかけるのをやめて後ろをついていく。辺りは暗く、冷えた空気がぴたりと身体に張り付き、芯から熱を奪っていく。
「ねえ、どこに行くの」
昨日、陽が昇る前に出かけるから準備をしろと言われた。朝日の気配が微塵も感じられない今、いつもと印象の違う外套を着た彼が、約束通り迎えに来たところだ。季節は真冬。加えて熱源は己の身体のみ。いくら厚めの上着を着ていても、寒さで唇がわななく。
「ねえ」
「静かにしろ。見つかるだろうが」
ちっとも説明をする気のない背中を半眼で見つめ、相変わらず強引だなとため息をつく。空を見上げれば、ちらちらと星が静かに瞬いていた。きんと冷えた空気に、雪が降りそうだと思う。
静かな空間に二人の足音だけが落ちる中、裏門の近くに何かが見えた。同時に、動物の気配を感じ取る。馬だ。小さな嘶きと共に、足を軽く踏み鳴らしている。
「悪い。待たせたな」
何度か見かけたことのある年配の男性。確か厩番の人だ。「久々ですね」と呆れたように彼に笑いかけている。
「……馬に乗るの?」
「ああ」
こちらを見ることなく答えた彼は、あっという間に馬上の人となってしまう。そして私に向かって手を伸ばした。
「ほら」
こうして、何度も馬に乗ったのはいつだったか。この人が馬にだけは優しいと思ったこともあった。
硬い、私より大きな手を掴めば、あっという間に馬の上へと引き上げられる。彼の手は、熱かった。
「あまり遅くなりませぬよう……」
「わかってる。心配をかけない内に戻る」
「……それは無理ではないかと」
苦笑しながら拱手し頭を垂れた男性を横目に、手綱をしっかりと握らされた。
「ちゃんと握っとけよ」
「う、うん」
馬は何度乗っても慣れない。一人で乗れないからだろうか。どしりとした足元の馬の体幹と、背中の彼の気配で不安は感じないものの、生き物の上に跨るのは独特の緊張感がある。ぶるる、と馬が鼻を鳴らしながら首を振った。
「行くぞ」
ぐっと身体に力を込め最初の揺れに耐えてしまえば、重い振動も軽やかなリズムに飲み込まれ気にならなくなる。
寝静まった街の中を、馬はどんどん駆けていく。時折灯りと笑い声が響く店がある以外は、本当に静かだ。思えばこんな暗い時間に馬に乗るのは初めてで、前方がよく見えず不安になる。
「ねえ」
城を出たからいいだろう、と少し声を張り上げれば、「なんだ」と声が降ってきた。
「どこに行くの?」
「何でそんなに気にするんだよ」
「……普通するよ」
ぶつかってくる冬の冷たい空気に、露出した部分がちりちりと痛む。手綱を離すわけにもいかず、外套を上げることすら叶わない。これ以上聞く気もなくして、かじかむ手で手綱を離さぬよう、握りしめることに集中した。
そうこうしている内に、あっという間に門前まで辿り着いた。門番と二、三やりとりを交わし、馬の足音を響かせ街の城門を抜ける。街中ではないから灯りもない。かろうじて判別できるのは道ぐらいだ。その中をひたすらどこかへ向かって走っていく。本当にどこに行くつもりだろう、と思っていると彼が喋りはじめた。
「久々に時間が空いたからな。少し遠出するぞ」
「……内緒でお出かけなの?」
「まあな。昔はよくやってた」
彼が笑った気配がする。その顔を思い浮かべて、小さく笑みをこぼす。
ふいに、うっすらと暗闇が遠のき始めた。ぼんやり眺めていると、黒い山々の稜線に光が走る。それは数度瞬きする間にも色を変え続け、天地の境界をはっきりと染め上げていく。思わずため息がこぼれた。
馬の走る速度は落ちない。でもきっと彼もこの光景を見ているだろう。
「綺麗だね、──」
喉が張り付いていて、一瞬息ができなかった。
大きく喉を上下させ唾を飲み込み、ぱちぱちと瞬きを繰り返す。身体が、酷く冷えている。
自分の身体を見下ろせば、掛布団がベッドからずり落ちていた。それは寒いはずだ。風邪を引くかもしれない、とぼんやりした頭で思う。
身体を動かすのも億劫で、視線だけで辺りを見渡す。見慣れた天井、カーテン。外は次第に明るくなってきているらしく、部屋の中は容易に見渡せた。目覚まし時計に手を伸ばして確認すれば、日の出を少し過ぎた頃だ。
『綺麗だね、 』
また、あの人の夢を見た。
息を細く吐いて、力の入らない腕で何とか起き上がる。
カーテンを開けてみると、ちょうど建物との境目を滲ませながら、朝陽が昇っているところだった。溶けたオレンジ色が、徐々に丸く、そして見ることを拒絶するように光を強めていく。目を細めて逸らし、カーテンを閉じた。
今のより、綺麗な朝焼けだった。馬なんて一度も乗ったことがないのに、揺れる感触も、暖かな馬の胴体も、何故か知っているような気がする。
――あの人のことも、知っている。金色の髪。目の色は、青だったり灰色だったり、光の具合で違う。すぐ怒ったように話す。でも、優しい人だ。優しくて、強い人。
そこまで考えて、くすりと笑いがれこぼた。――夢なのに、『知ってる』なんて。けれども、確かめずにはいられなかった。
「……綺麗だね、」
自分が言った台詞を反芻してみても、確かに夢の中で呼びかけたはずの名前は出てこなかった。
息を吐く。今日は吐いた先から凍り付くように寒い。
首に巻いたマフラーを口元まであげれば、喉が少し痛いことに気が付いた。やはり風邪を引き始めている。
『体調悪いのか?いつからだ』
ふいに、あの人にかけられた言葉を思い出した。表情だって、思い出せる。今まで忘れていたというのに……。夢を見ると、こうして記憶になかったものが溢れることがある。
──ああ、駄目だ。今日は駄目な日だ。
唇を引き結ぶ。そうしなければ泣いてしまいそうだった。
名前も知らないあの人のことが、頭から離れない。話した記憶にない声が、頭の中を占めていく。
長く息を吐いて頭上を見上げれば、小さな白い欠片がふわふわと舞い降り始めていた。
──あの後、雪は降ったのだろうか。
舞い降りる雪は小さすぎて、触れるか触れないかの距離で消えてしまう。あの人のことも同じ。痕跡を探そうとすればするほど、輪郭がぼやけてしまう。今頭の中を占めている声も、表情も。夢を見るたびに思い出しては消えていくのだ。
具体的なことは何一つ残ってくれないのに、あの人への気持ちだけが結晶みたいに綺麗に整えられていく。
堪えきれなくなった雫が、熱く頬を滑り落ちていく。
でも、覚えていたいわけではないのだ。だって、必要がない。他愛なく交わした言葉も。隠し事ができないから、すぐに変わる表情も。自分よりも他を優先する強さからくる優しさも――。『選ばなかった』私には、全部、全部、必要のないものだ。どうせ、これもすぐに忘れてしまう。
『誰』とか、そんなのどうでもいい。
あなた以上に好きだと思える人がいないことだけを、私は覚えていればいい。
『揺れる、ゆれる』 #仲花
以前書いた『誰がために ―秘め事―』で出てくる髪飾りのお話。
****************
「あ」
蒼いまあるいそれは、手からするりと逃げるように落ちて行った。
「何だよ」
「あ、ううん。何でも」
慌てて拾い上げた物をじっと見つめる。見た所ヒビもなく大事はなさそうで、胸を撫でおろした。
「……それ」
花の部屋で茶を飲んでいた仲謀が、手を止めてこちらをじっと見つめる。
「あ、仲謀が前にくれたやつだよ」
あの時は冬だった。うららかな気候の今と対照的な、凍える日々を思い出す。花の手には、以前仲謀から贈られた──押し付けられたに近いもしれない──玉が握られていた。
「革袋の紐につけてたんだけど、ほどけちゃったみたいで」
「……全然見ねえと思ったら地味なとこにつけやがって」
「地味って……。大事にしてたんだよ」
これならどこへでも持っていくものだし、と丈夫な皮袋ごと見せつける。
「そういえば、仲謀と出掛けた時に買ったんだよね、これ」
「そういえばって」
忘れてたのかよ、と舌打ちをする仲謀に首を傾げる。
「……何で機嫌悪いの?」
「悪くねえ」
ぐい、と残りの茶を煽り、仲謀が立ち上がって花の傍に寄ってきた。婚儀までもう少し。部屋は移動することになるからと、あまり持ち物があるわけではなかったが、整理をしているところだ。
「ちょっと貸せ」
ひょいと手の中の玉を奪い取られ、玉越しにじいっと見つめられ、思わずたじろいだ。
「な、何」
「これ借りとくぞ」
「へ?」
そのまま懐に収められ、目を瞬かせることしかできない。そうしていると、仲謀に髪を一房救い取られた。
「っ!」
「お前、髪は結わないのか」
「……髪?」
仲謀の長い指が頬に触れそうで、気もそぞろに答える。
「あんまり、しないかも……」
「ふうん」
生返事の後の考え込むような仕草。つい、疑問が口をついて出た。
「……結ってる方が好き?」
今のままでは駄目なのだろうか。そんな不安が知らず漏れだして、思ったよりも弱弱しい声になる。仲謀はというと、弾けるように手を髪から外した。
「そ、そういうわけじゃない!」
「……」
「そうじゃなくて、……普通、何か、結い上げたりとか着飾ったりとか。そういうの好きだろ」
「まあ、それはそうだけど」
おしゃれは楽しいし、好きな方だとは思う。最近の婚儀の衣装選びだって、大変であったものの最初の頃は心が躍った。──さすがに何度も何度も続いたため、辟易しているのだが。
「だから、……」
「だから?」
「──何でもねえ。じゃあな」
そのまま踵を返して部屋を出て行ってしまった。
──あれ、気に入ってたんだけどな。
仲謀が持って行ってしまった玉のことを思い出しながら、すっかり色をなくしてしまった皮袋を見つめた。
◇
「花様。仲謀様がお呼びです」
花嫁修業の一環として始めた恒例の書き取りをしていると、侍女が花を呼びに来た。本人ではなくわざわざ侍女をやるとは珍しい。数日前の彼の不可解な行動を思い出しながら、首を傾げる。
少し前まで使用人が出入りするのみだった花の部屋は、正式に婚姻が決まってから部屋付きの侍女まで与えられていた。とはいえ元々は客室。普段は別の部屋に待機しており、用があるとこうして出向いてくれている。
「……仲謀が?」
「はい。……お急ぎの様でした」
眉を下げ困った顔を見せる侍女に、慌てて筆の処理をして仕舞う。迷惑を被るのは侍女の方だ。立ち上がってぱたぱたと身だしなみが乱れていないか確認していると、彼女がくすりと笑って背中のよれを直してくれた。
「ありがとうございます」
「いえ、気になさらないでください」
世話をされることには慣れないものの、こうして笑顔を向けてくれる存在がいると安心できるものだと、侍女をつけてくれたことには感謝していた。欲を言えば、対等に話せる友達が欲しいのだけれど──。それは立場上難しいことも理解していた。ふと、玄徳軍にいる芙蓉姫のことを思い出し、鼻先がつんとしそうになるのを堪えた。
侍女を連れて仲謀の部屋へ向かおうとすると、別の方向を示される。あまり出向いたことのない方角だ。来客時に使う部屋が多かったように思う。見慣れぬ扉の前に案内をされ、侍女が戸を叩く。
「花様をお連れしました」
「入れ」
戸越しに聞こえた仲謀の声に肩の力を抜きながら入室すると、卓の上に色とりどりの装飾品が並べられている光景が目に入り、その場で立ち止まってしまった。
「何ぼうっとしてんだよ」
「……え、うん」
そろそろと入室して仲謀の横に並ぶ。卓の向こう側には人好きそうな顔をした年配の男性が笑顔で立っていた。何だろう、これは。
「どれがいいと思う」
「……何の話?」
仲謀は見てわかるだろとも言わんばかりに説明を省くことがある。おそるおそる聞けば、ばかにしたような目で見下ろされる。
「どれって。お前の装飾品だよ」
「……婚儀の?」
「婚儀のはもう決めただろうが。普段使うものだよ」
ふと、先日の髪を結わないのか、という会話が蘇った。
「……仲謀」
「何だ」
おそらく目の前の男性は城お抱えの商人なのだろう。その人物を前にして言うのはなんだが、言うべきことは言っておかねばと丹に力を込めた。
「私、あまり贅沢はしなくていいんだけど──」
「お前な、孫家の嫁だぞ。これぐらいで贅沢とか言ってんじゃねえ」
そうくると思った。想定内の答えに、落ち着いて花は返す。
「これは贅沢の範疇だよ」
「~~っ、お前はいっつもいっつも人の好意をなんだと」
「いつもっていつの話──」
「はああ?」
「花様……」
遠慮したような侍女の小さな声に我に返る。いけない、今ここで喧嘩するようなことではない。落ち着かせようとちらりと侍女を見れば、うんうんと力強く頷きを繰り返していた。……大人しく受けとれということなのだろう。
内心溜息を吐きながら、ありがとうと義理で言えば鼻をならされる。
「最初っからそう言えばいいんだよ」
……このまま部屋を出て行きたい、など不穏なことを考えていると、侍女に小さく、けれど先程より強い口調で花様と窘められた。仲謀より、付き合いの短い侍女の方が花のことを理解してくれている気になる。しかし、仲謀のこういう態度は今に始まったことではないと、自分で自分を窘める。
さてと気を取り直し、目の前に並ぶ装飾品の数々に向き直る。急なことで圧倒されてよく見てはいなかったが、露天に並んでいたら確実に寄ろうと思っただろう。そんな魅力的な品々が丁寧に並べられている。が、未完成のようなパーツのみの物が多いようで首を傾げる。
「どれにする」
そう言いながら仲謀が懐から先日預かっていった玉を取り出した。
「それ……」
「どれでも好きなものに加工してもらえるぞ」
「え……」
まさかここでその玉が出てくるとは思わず、仲謀と玉を交互にまじまじと見つめる。借りるぞ、とはこのことだったのか。
「……何で持っていったの?」
今ここで花に選ばせるなら、持っていく必要などなかったのではないだろうか。
そう聞けば、罰が悪そうに目を逸らされた。
「……何に加工するか大喬達に聞いたら、お前に決めさせろって言うから」
段々と小さくなる声とは裏腹に、花の脈が早まる。─嬉しい。素直に、そう思った。
「ありがとう」
改めて、心からそう言えば仲謀の耳が赤みを帯びる。
「いいから早く選べよ」
仲謀のその様子に、緩みそうになる頬を抑えることに失敗しながら、装飾の希望を伝えた。
◇
てきぱきと、そして鮮やかとでもいうべき手つきで、髪が結い上げられていく。先ほどの装飾品をつけるならと、侍女に髪を整えてもらっているところだ。
「仲謀様をお呼びして参りますね」
心なしかいつもより笑顔を携えながら仕事を成し遂げた侍女は、一礼して優雅に退室していった。鏡の中の自分を見つめてどきどきする。見慣れない姿は心が踊るような、知らない自分を見つけて不安でもある。
すぐに仲謀の声が聞こえると同時に、部屋に入ってきた。一層鼓動が早まるのを感じながら、開口一番に「どうかな」と感想を聞いてみる。
「……まあ、悪くないんじゃねえの」
言葉だけを捉えれば不満だが、今にも破顔しそうな顔で言われると笑わざるを得ない。くすくすと笑い出すと、不機嫌そうな顔に変わった。
「なんだよ」
「別に。……つけてくれる?」
仲謀の手元には、先ほど作ってもらったばかりの簪。蒼い玉と、それに合わせて選ばれた複数の小さな玉が簪の先から垂れ下がり、室内に入り込んだ陽光を受け、動きに合わせて光を散らしている。
「これで良かったのかよ」
「うん」
『仲謀に決めて欲しい』
花が出した要望はそれだけだった。元々彼が花に似合うものを考えてくれる予定だったのだろう。それが何よりも嬉しいと思い、そう伝えた。
「すごく可愛い。この玉も気に入ってたから、嬉しい」
「……そうかよ」
仲謀がほっとしたように顔を緩ませて、花の頭にそっと触れて簪を差し込んだ。
「どう?」
「……似合ってるよ」
先程とは打って変わって素直に褒めるものだから、花も頬を赤らめ俯いた。
「だ、大事にするね」
「当たり前だ」
簪が差された辺りがくすぐったいし、首元はやたらと風通しがいいやらで落ち着かない気分だ。
少しでも身じろぎすれば、しゃらしゃらと細い音が聞こえるのが、何とも気恥ずかしい。着飾るのは、玄徳軍の宴に出た時以来だなとふと思った。
「あ、なんかお返ししたいんだけど──。欲しいものとか、ある?」
照れ臭さを誤魔化すように早口で伝えれば、別にないと返ってくる。
「でも貰ってばっかりだし」
「いいんだよ。それくらい。──俺は、そのくらいしかしてやれねえんだから」
その響きに、どくりと心臓が嫌な音を立てた。いつもの、特になんてことない顔をしているのに。声だけが、何かを含んでいる。
彼は負う必要のないことについて考えているのではないだろうか。自信の想像に焦り、仲謀の袖を掴んだ。
「花?」
「──私、」
幸せだよ? ここに残って良かったよ? いくつも浮かんでは消えていく言葉。仲謀がいてくれれば何もいらないと思うのに、言葉にすると色あせて、あるいは嘘になってしまいそうで──。怖くて口にすることができない。
「……ありがとう」
「……急になんだよ」
結局不自然に礼を繰り返す花に、仲謀が戸惑いつつも笑う。その笑顔に胸が締め付けられる。
仲謀以上に好きな人なんて出来ないと思った。その気持ちが私をここに繋ぎ止め、仲謀の作る未来を見たいと思わせた。だから、だからこの人が気にすることなんて何一つないのに。私が仲謀を好きだという気持ちが彼を悩ませてしまうのだとしたら──。それは、あまりにも悲しい。
「──どうした」
仲謀の手の甲で、頬を撫でるように触れられた。心配する声音に、酷い顔をしているのだろうと首を振り、笑って見せた。
「仲謀のこと、好きだなと思って」
先ほどは出なかった言葉がするりと出る。誤魔化すために、軽口のようになら好意を素直に伝えられたことに、軽く失望した。これじゃ嘘みたい。
「……」
仲謀が何かを言いかけようとして、溜息を洩らした。そうして視線がさ迷った後、両肩に手を置かれた。
仲謀が少し屈んだところで、次の行動を察して花は静かに目線をあげる。顔が近づいて、最初に前髪が少しだけ触れて、そこで初めて目を閉じた。静かに唇に触れた熱。角度を変えて啄ばむように食まれる感触に背筋が震えた。
──嘘じゃない。本当に仲謀のことが好きなのだと、踵を浮かせて彼の唇を食むように返せば、一瞬動きを止めたあとに舌が差し込まれた。
「……っ、ふ」
口内に溢れる質量に思わず声が漏れれば、そっと後頭部に手を添えられ、動けなくなる。
何かを誤魔化すように始まった深い口付けは、二度ほど繰り返されたところで、仲謀から離れることで終えた。
軽く肩を揺らして息をすると、仲謀の熱を帯びた瞳に覗き込まれた。今度は甘く痺れを伴いどきりと心臓が大きく音を立てた。
そうして、そのまま花の肩口に仲謀の額を預けられた。
「……早く婚儀にならねえかな」
「……そればっかり」
どくどくと早鐘を打つ心臓の音が煩わしい。『これ以上』の行為を求めて婚儀を待ち望む仲謀のことを、いつしか非難できなくなっている自分がいる。──もう別にいいんじゃないかな。不意にそんなことを思うことがある。だが、実際に『これ以上』の内容が具体的にわからないし、その時が来たら怖気づくような気もする。
だから「いいよ」とも言えず、代わりに頬を仲謀の頭に摺り寄せた。
「毎日つけるね」
仲謀の頭は依然として花の肩に乗ったままだから、自然と彼の耳が近くなる。耳を傷めないよう声を細めてそう伝えれば、仲謀が顔をあげて身を離してしまった。
「……いや、たまにでいい」
「え、でも、せっかく貰ったし。……それに、結い上げる方が好きでしょ?」
離れてしまった距離に寂しさを覚えつつ、簪をつけなくていいと言う仲謀に首を傾げる。てっきりつけて欲しがるぐらいだと思ったのに。
「誰がそんなこと言ったんだよ」
「……違うの?」
「……お前の髪に触れられない」
言いながら、耳の辺りを仲謀の長い綺麗な指がそっと掠めていく
不意に、常ならば口付けの時に髪に差し込まれる指の動きを、その感触を思い出し、再び熱が立ち昇ってくる。
「っ、……」
「あと」
思わず恥ずかしさで顔を俯かせていると、独り言のように仲謀が言葉を零した。
「堪えられる自信もねえし……」
不可解な言葉に熱も忘れ仲謀を見上げれば、明後日の方向を見ながら頬を染めていた。
「……何が?」
「いや項が──って何でもないからな‼」
「……? なに?」
「いい!わからないでいいから!忘れろ‼」
頭を鷲掴みにされ、がくがくと揺らされる。
「ちょ、ちょっと!」
「あと今日は部屋から出るな!」
「何それ、横暴すぎるよ!」
「うるせえ、これは命令だ‼」
久々に聞いた言葉に思わず吹き出すと、仲謀がなんだよ、と不機嫌そうな顔する。
頭から放れた手を軽く握りながら、こうして無邪気に触れ合える今も愛しいと。思わず笑みが零れた。
以前書いた『誰がために ―秘め事―』で出てくる髪飾りのお話。
****************
「あ」
蒼いまあるいそれは、手からするりと逃げるように落ちて行った。
「何だよ」
「あ、ううん。何でも」
慌てて拾い上げた物をじっと見つめる。見た所ヒビもなく大事はなさそうで、胸を撫でおろした。
「……それ」
花の部屋で茶を飲んでいた仲謀が、手を止めてこちらをじっと見つめる。
「あ、仲謀が前にくれたやつだよ」
あの時は冬だった。うららかな気候の今と対照的な、凍える日々を思い出す。花の手には、以前仲謀から贈られた──押し付けられたに近いもしれない──玉が握られていた。
「革袋の紐につけてたんだけど、ほどけちゃったみたいで」
「……全然見ねえと思ったら地味なとこにつけやがって」
「地味って……。大事にしてたんだよ」
これならどこへでも持っていくものだし、と丈夫な皮袋ごと見せつける。
「そういえば、仲謀と出掛けた時に買ったんだよね、これ」
「そういえばって」
忘れてたのかよ、と舌打ちをする仲謀に首を傾げる。
「……何で機嫌悪いの?」
「悪くねえ」
ぐい、と残りの茶を煽り、仲謀が立ち上がって花の傍に寄ってきた。婚儀までもう少し。部屋は移動することになるからと、あまり持ち物があるわけではなかったが、整理をしているところだ。
「ちょっと貸せ」
ひょいと手の中の玉を奪い取られ、玉越しにじいっと見つめられ、思わずたじろいだ。
「な、何」
「これ借りとくぞ」
「へ?」
そのまま懐に収められ、目を瞬かせることしかできない。そうしていると、仲謀に髪を一房救い取られた。
「っ!」
「お前、髪は結わないのか」
「……髪?」
仲謀の長い指が頬に触れそうで、気もそぞろに答える。
「あんまり、しないかも……」
「ふうん」
生返事の後の考え込むような仕草。つい、疑問が口をついて出た。
「……結ってる方が好き?」
今のままでは駄目なのだろうか。そんな不安が知らず漏れだして、思ったよりも弱弱しい声になる。仲謀はというと、弾けるように手を髪から外した。
「そ、そういうわけじゃない!」
「……」
「そうじゃなくて、……普通、何か、結い上げたりとか着飾ったりとか。そういうの好きだろ」
「まあ、それはそうだけど」
おしゃれは楽しいし、好きな方だとは思う。最近の婚儀の衣装選びだって、大変であったものの最初の頃は心が躍った。──さすがに何度も何度も続いたため、辟易しているのだが。
「だから、……」
「だから?」
「──何でもねえ。じゃあな」
そのまま踵を返して部屋を出て行ってしまった。
──あれ、気に入ってたんだけどな。
仲謀が持って行ってしまった玉のことを思い出しながら、すっかり色をなくしてしまった皮袋を見つめた。
◇
「花様。仲謀様がお呼びです」
花嫁修業の一環として始めた恒例の書き取りをしていると、侍女が花を呼びに来た。本人ではなくわざわざ侍女をやるとは珍しい。数日前の彼の不可解な行動を思い出しながら、首を傾げる。
少し前まで使用人が出入りするのみだった花の部屋は、正式に婚姻が決まってから部屋付きの侍女まで与えられていた。とはいえ元々は客室。普段は別の部屋に待機しており、用があるとこうして出向いてくれている。
「……仲謀が?」
「はい。……お急ぎの様でした」
眉を下げ困った顔を見せる侍女に、慌てて筆の処理をして仕舞う。迷惑を被るのは侍女の方だ。立ち上がってぱたぱたと身だしなみが乱れていないか確認していると、彼女がくすりと笑って背中のよれを直してくれた。
「ありがとうございます」
「いえ、気になさらないでください」
世話をされることには慣れないものの、こうして笑顔を向けてくれる存在がいると安心できるものだと、侍女をつけてくれたことには感謝していた。欲を言えば、対等に話せる友達が欲しいのだけれど──。それは立場上難しいことも理解していた。ふと、玄徳軍にいる芙蓉姫のことを思い出し、鼻先がつんとしそうになるのを堪えた。
侍女を連れて仲謀の部屋へ向かおうとすると、別の方向を示される。あまり出向いたことのない方角だ。来客時に使う部屋が多かったように思う。見慣れぬ扉の前に案内をされ、侍女が戸を叩く。
「花様をお連れしました」
「入れ」
戸越しに聞こえた仲謀の声に肩の力を抜きながら入室すると、卓の上に色とりどりの装飾品が並べられている光景が目に入り、その場で立ち止まってしまった。
「何ぼうっとしてんだよ」
「……え、うん」
そろそろと入室して仲謀の横に並ぶ。卓の向こう側には人好きそうな顔をした年配の男性が笑顔で立っていた。何だろう、これは。
「どれがいいと思う」
「……何の話?」
仲謀は見てわかるだろとも言わんばかりに説明を省くことがある。おそるおそる聞けば、ばかにしたような目で見下ろされる。
「どれって。お前の装飾品だよ」
「……婚儀の?」
「婚儀のはもう決めただろうが。普段使うものだよ」
ふと、先日の髪を結わないのか、という会話が蘇った。
「……仲謀」
「何だ」
おそらく目の前の男性は城お抱えの商人なのだろう。その人物を前にして言うのはなんだが、言うべきことは言っておかねばと丹に力を込めた。
「私、あまり贅沢はしなくていいんだけど──」
「お前な、孫家の嫁だぞ。これぐらいで贅沢とか言ってんじゃねえ」
そうくると思った。想定内の答えに、落ち着いて花は返す。
「これは贅沢の範疇だよ」
「~~っ、お前はいっつもいっつも人の好意をなんだと」
「いつもっていつの話──」
「はああ?」
「花様……」
遠慮したような侍女の小さな声に我に返る。いけない、今ここで喧嘩するようなことではない。落ち着かせようとちらりと侍女を見れば、うんうんと力強く頷きを繰り返していた。……大人しく受けとれということなのだろう。
内心溜息を吐きながら、ありがとうと義理で言えば鼻をならされる。
「最初っからそう言えばいいんだよ」
……このまま部屋を出て行きたい、など不穏なことを考えていると、侍女に小さく、けれど先程より強い口調で花様と窘められた。仲謀より、付き合いの短い侍女の方が花のことを理解してくれている気になる。しかし、仲謀のこういう態度は今に始まったことではないと、自分で自分を窘める。
さてと気を取り直し、目の前に並ぶ装飾品の数々に向き直る。急なことで圧倒されてよく見てはいなかったが、露天に並んでいたら確実に寄ろうと思っただろう。そんな魅力的な品々が丁寧に並べられている。が、未完成のようなパーツのみの物が多いようで首を傾げる。
「どれにする」
そう言いながら仲謀が懐から先日預かっていった玉を取り出した。
「それ……」
「どれでも好きなものに加工してもらえるぞ」
「え……」
まさかここでその玉が出てくるとは思わず、仲謀と玉を交互にまじまじと見つめる。借りるぞ、とはこのことだったのか。
「……何で持っていったの?」
今ここで花に選ばせるなら、持っていく必要などなかったのではないだろうか。
そう聞けば、罰が悪そうに目を逸らされた。
「……何に加工するか大喬達に聞いたら、お前に決めさせろって言うから」
段々と小さくなる声とは裏腹に、花の脈が早まる。─嬉しい。素直に、そう思った。
「ありがとう」
改めて、心からそう言えば仲謀の耳が赤みを帯びる。
「いいから早く選べよ」
仲謀のその様子に、緩みそうになる頬を抑えることに失敗しながら、装飾の希望を伝えた。
◇
てきぱきと、そして鮮やかとでもいうべき手つきで、髪が結い上げられていく。先ほどの装飾品をつけるならと、侍女に髪を整えてもらっているところだ。
「仲謀様をお呼びして参りますね」
心なしかいつもより笑顔を携えながら仕事を成し遂げた侍女は、一礼して優雅に退室していった。鏡の中の自分を見つめてどきどきする。見慣れない姿は心が踊るような、知らない自分を見つけて不安でもある。
すぐに仲謀の声が聞こえると同時に、部屋に入ってきた。一層鼓動が早まるのを感じながら、開口一番に「どうかな」と感想を聞いてみる。
「……まあ、悪くないんじゃねえの」
言葉だけを捉えれば不満だが、今にも破顔しそうな顔で言われると笑わざるを得ない。くすくすと笑い出すと、不機嫌そうな顔に変わった。
「なんだよ」
「別に。……つけてくれる?」
仲謀の手元には、先ほど作ってもらったばかりの簪。蒼い玉と、それに合わせて選ばれた複数の小さな玉が簪の先から垂れ下がり、室内に入り込んだ陽光を受け、動きに合わせて光を散らしている。
「これで良かったのかよ」
「うん」
『仲謀に決めて欲しい』
花が出した要望はそれだけだった。元々彼が花に似合うものを考えてくれる予定だったのだろう。それが何よりも嬉しいと思い、そう伝えた。
「すごく可愛い。この玉も気に入ってたから、嬉しい」
「……そうかよ」
仲謀がほっとしたように顔を緩ませて、花の頭にそっと触れて簪を差し込んだ。
「どう?」
「……似合ってるよ」
先程とは打って変わって素直に褒めるものだから、花も頬を赤らめ俯いた。
「だ、大事にするね」
「当たり前だ」
簪が差された辺りがくすぐったいし、首元はやたらと風通しがいいやらで落ち着かない気分だ。
少しでも身じろぎすれば、しゃらしゃらと細い音が聞こえるのが、何とも気恥ずかしい。着飾るのは、玄徳軍の宴に出た時以来だなとふと思った。
「あ、なんかお返ししたいんだけど──。欲しいものとか、ある?」
照れ臭さを誤魔化すように早口で伝えれば、別にないと返ってくる。
「でも貰ってばっかりだし」
「いいんだよ。それくらい。──俺は、そのくらいしかしてやれねえんだから」
その響きに、どくりと心臓が嫌な音を立てた。いつもの、特になんてことない顔をしているのに。声だけが、何かを含んでいる。
彼は負う必要のないことについて考えているのではないだろうか。自信の想像に焦り、仲謀の袖を掴んだ。
「花?」
「──私、」
幸せだよ? ここに残って良かったよ? いくつも浮かんでは消えていく言葉。仲謀がいてくれれば何もいらないと思うのに、言葉にすると色あせて、あるいは嘘になってしまいそうで──。怖くて口にすることができない。
「……ありがとう」
「……急になんだよ」
結局不自然に礼を繰り返す花に、仲謀が戸惑いつつも笑う。その笑顔に胸が締め付けられる。
仲謀以上に好きな人なんて出来ないと思った。その気持ちが私をここに繋ぎ止め、仲謀の作る未来を見たいと思わせた。だから、だからこの人が気にすることなんて何一つないのに。私が仲謀を好きだという気持ちが彼を悩ませてしまうのだとしたら──。それは、あまりにも悲しい。
「──どうした」
仲謀の手の甲で、頬を撫でるように触れられた。心配する声音に、酷い顔をしているのだろうと首を振り、笑って見せた。
「仲謀のこと、好きだなと思って」
先ほどは出なかった言葉がするりと出る。誤魔化すために、軽口のようになら好意を素直に伝えられたことに、軽く失望した。これじゃ嘘みたい。
「……」
仲謀が何かを言いかけようとして、溜息を洩らした。そうして視線がさ迷った後、両肩に手を置かれた。
仲謀が少し屈んだところで、次の行動を察して花は静かに目線をあげる。顔が近づいて、最初に前髪が少しだけ触れて、そこで初めて目を閉じた。静かに唇に触れた熱。角度を変えて啄ばむように食まれる感触に背筋が震えた。
──嘘じゃない。本当に仲謀のことが好きなのだと、踵を浮かせて彼の唇を食むように返せば、一瞬動きを止めたあとに舌が差し込まれた。
「……っ、ふ」
口内に溢れる質量に思わず声が漏れれば、そっと後頭部に手を添えられ、動けなくなる。
何かを誤魔化すように始まった深い口付けは、二度ほど繰り返されたところで、仲謀から離れることで終えた。
軽く肩を揺らして息をすると、仲謀の熱を帯びた瞳に覗き込まれた。今度は甘く痺れを伴いどきりと心臓が大きく音を立てた。
そうして、そのまま花の肩口に仲謀の額を預けられた。
「……早く婚儀にならねえかな」
「……そればっかり」
どくどくと早鐘を打つ心臓の音が煩わしい。『これ以上』の行為を求めて婚儀を待ち望む仲謀のことを、いつしか非難できなくなっている自分がいる。──もう別にいいんじゃないかな。不意にそんなことを思うことがある。だが、実際に『これ以上』の内容が具体的にわからないし、その時が来たら怖気づくような気もする。
だから「いいよ」とも言えず、代わりに頬を仲謀の頭に摺り寄せた。
「毎日つけるね」
仲謀の頭は依然として花の肩に乗ったままだから、自然と彼の耳が近くなる。耳を傷めないよう声を細めてそう伝えれば、仲謀が顔をあげて身を離してしまった。
「……いや、たまにでいい」
「え、でも、せっかく貰ったし。……それに、結い上げる方が好きでしょ?」
離れてしまった距離に寂しさを覚えつつ、簪をつけなくていいと言う仲謀に首を傾げる。てっきりつけて欲しがるぐらいだと思ったのに。
「誰がそんなこと言ったんだよ」
「……違うの?」
「……お前の髪に触れられない」
言いながら、耳の辺りを仲謀の長い綺麗な指がそっと掠めていく
不意に、常ならば口付けの時に髪に差し込まれる指の動きを、その感触を思い出し、再び熱が立ち昇ってくる。
「っ、……」
「あと」
思わず恥ずかしさで顔を俯かせていると、独り言のように仲謀が言葉を零した。
「堪えられる自信もねえし……」
不可解な言葉に熱も忘れ仲謀を見上げれば、明後日の方向を見ながら頬を染めていた。
「……何が?」
「いや項が──って何でもないからな‼」
「……? なに?」
「いい!わからないでいいから!忘れろ‼」
頭を鷲掴みにされ、がくがくと揺らされる。
「ちょ、ちょっと!」
「あと今日は部屋から出るな!」
「何それ、横暴すぎるよ!」
「うるせえ、これは命令だ‼」
久々に聞いた言葉に思わず吹き出すと、仲謀がなんだよ、と不機嫌そうな顔する。
頭から放れた手を軽く握りながら、こうして無邪気に触れ合える今も愛しいと。思わず笑みが零れた。
『誰がために ―秘め事―』 #仲花
webオンリー用に、本来書きたかったものの後日談として書きました。そっちの方はまだ完成していませんが必ず完成させます。
拙さ全開で書き直したいものの、一番見て頂いたものなのでそのままにしています。
****************
どこまでも濃い青空が窓から見える。蝉の声に、大きな入道雲。この世界に来て初めての夏は後半に向かっていた。汗はともかく、入り込んでくる夏の気配は心地良い。食後のお茶を用意していた年配の使用人が、にこにこと話し出した。
「そういえば、仲謀様がお生まれになった時も、こんな陽気でしたねえ」
「……仲謀って夏生まれなんですか?」
「ええ。とても天気のよい日でしたよ」
懐かしそうに目元を綻ばせて、仲謀に笑いかける。
「本当に大きく立派になられて」
「――それはもういい」
ややうんざりした様に仲謀が返す。恥ずかしいならそう言えばいいのに。たまに来るこの使用人は、元々は呉夫人に仕えていたらしく、度々思い出話をしては仲謀を照れさせていた。仕事を終えた彼女は、くすくすと笑いながら一礼をして退室していく。
「そっか、夏なんだ」
すごく『ぽいなあ』と思った。夏の日差しに反射する彼の金の髪は綺麗だから。
「もう過ぎてるけどな」
「そうなの?」
こちらでは誕生日を当日に祝ったりしないのだろうか。疑問に思って聞いてみると、どうやら生まれた日ではなく、年を取るのも贈り物をするのも、年明けに行う習慣らしい。
「私の世界だと、生まれた日が特別で、その日に年を取るんだ」
そういえば、昔は年齢の数え方が違った、という話を聞いたことがあるかもしれない。そもそも国自体が違うわけだし――と考え込んでいると、仲謀がじっとこちらを見ていることに気がついた。
「……特別って何かするのか?」
「誕生日?そうだね――」
ふと、よぎった記憶に思わず言い淀む。
「……え、と。御馳走食べたり、とか。プレゼントも」
今年のプレゼントは、ゲームだった。ごちそうを作らなきゃと張り切る母に頼まれた、弟の誕生日プレゼント。タイトルは携帯にメモしていたから、もう思い出すこともない。誕生日にいなくなった姉を、家族はどう思っているのだろう――。
「ぷれぜんと?」
不思議そうに聞き返す仲謀の声に、現実に引き戻される。
「あ、贈り物のことだよ」
「……へえ。あまりこっちと変わらないんだな」
「そう、だね」
変わらないのだろうか。今までこの世界に過ごしてきた中で、元の世界と変わらないものはあまり見当たらない。お祝い一つとってみても、やはり馴染みのない儀式的なものが多く、同じとは言い難いのではないかと思う。
「――お前は」
「?」
「いつなんだ?生まれた日は」
「私?春だよ」
もうとっくに過ぎていることを伝えると、仲謀が眉根を寄せた。
「何で言わねえんだよ」
「……え、何でって。私も忘れてたし。仲謀だって言わなかったじゃない」
正直、誕生日当日にあまり意味がないことを知って、ほっとしていた。自分が生まれた日という、どうやっても元の世界に残してきた家族と直結することを、考えられる余裕は自分にはまだない。胸の辺りに巣食った罪悪感という名のしこりが痛むのだ。
ふと、仲謀を見ると怒ったような顔で黙り込んでいた。
「……どうしたの?」
「……何でもねえ」
そう言って立ち上がると、上着を着始めてしまう。
「もう行くの?」
「ああ」
「……いってらっしゃい」
――さっきまで機嫌悪そうじゃなかったのに。出会ったときよりはわかることも増えたけれど、未だに仲謀の機嫌のスイッチは不明な部分がある。振り返りもせず戸を閉めた仲謀の背中を思い出して、無意識に溜息を吐いた。
******
「おい、公瑾。いるか」
「仲謀様――。今からお伺いしようかと。何か急ぎの用でも?」
朝議よりも前に突然執務室に現れた主と話すため、書簡から目を上げた。難しい顔をしていた主を見て、何か良くない報せでも、と思わず身構える。
「祝うのに何をやったら喜ぶと思う」
「……は?」
予想外すぎる問いかけに思考が停止しそうになりながらも、とりあえず笑みを浮かべた。おそらく執務とは全然関係のない話だ。
「……奥方様のことでしょうか」
「そうだ」
――何故、私に聞くのだろう。軽い眩暈を覚えながら、何かめでたいことでも?と尋ねる。
「花が生まれた日を祝う。もう過ぎてるが」
――尚更、何故私に。そもそもそれは年明けに行うことが常であるし、今必要なことなのだろうか。思わず片手で顔を覆いながら、非常に面倒なことに巻き込まれているのでは?という疑念が浮かんでくる。
「そう、ですね……。女人への贈り物でしたら、定番は玉で――」
「あいつが喜ぶと思うか?」
「……いいえ」
普段の服装からして、華美なものを好むとは思えない。
「では、食べ物など」
「それは別に用意する」
即座に否定される。
「――何がいいのでしょうね」
至極どうでもいい。とりあえず山積みの仕事に目を向けて欲しい――。そんなことを考えながら仲謀を見ると、腕を組んで真剣な顔をして考え込んでいた。
その姿が公瑾の記憶の琴線に引っかかった。そして、糸を手繰り寄せてたどり着いた答えに、吐息が漏れる。避けていたとでも言うべき懐かしい情景の一つが蘇ってしまった。
「……時間はどうでしょうか」
「時間?」
「最近仲謀様はお忙しいですから――。お二人で出掛ける等、ゆっくり過ごされては如何ですか?」
執務の方は頑張って頂ければ埋め合わせもできましょう。
「……そうだな。そうする。邪魔したな」
納得した様子にこれで仕事も片付くだろう、と胸を撫でおろした時だった。
「やっぱりお前に聞いて良かった」
そう言い残して、彼は部屋を出て行った。
徐々に遠のいていく足音。静まり返った部屋の中で、頭の中には先ほど蘇ってしまった懐かしい声が響いている。
『兄上が喜ぶものは何でしょうか』
『だって、公瑾は兄上と一番仲が良いから』
『あと――』
思わず天を仰ぎ見る。そんなこともあった。珍しく後悔以外の念で昔を思い出した気がする。
『公瑾なら、必ず答えをくれると思って』
「……何故」
時を経て、昔と同じものなんてないと思っていたのに。
「変わらないんでしょうね、仲謀様は……」
揺るぎないその信頼は何なのだろう。それなのに、もたれ掛かるのではなく、自分の足でしっかりと自分の足で歩いていく。
『あいつは馬鹿正直でまっすぐだから、人の話をちゃんと聞くだろう。そうすると周りが放っておかない。――なあ、俺が頼まなくたって、お前はあいつのこと助けてやるだろ』
弟の才について嬉しそうに語る親友のことまで思い出してしまった。
仲謀の、『他者を切り捨てられない』あの優しさは乱世では危ういものだと、ずっと思っていた。だが、治世において、それは弱点にはならないのかもしれない。最近は、そう考えるようになっていた。
「――お前の言う通りだな」
ぽつりと漏らした言葉は、風に吹かれて消えていった。
******
仲謀が怒ったように出て行ったその日。夕食時も部屋には戻ってこず、執務室に籠りきりのようだった。それとなく使用人に尋ねると、「そういえば、今日はお忙しいようで姿を見ていませんね……」と返ってきた。いつもより忙しいのは間違いなさそうだった。
やはり何か怒っていたのだろうか。話がしたかったのだけれど、と無意識に溜息を零してしまう。とはいえ、夜も深まりいつ帰ってくるかわからない。そろそろ寝ようと立ち上がった時、やっと仲謀が帰ってきた。
「おかえ――」
「何だ起きてたのかよ。――丁度良かった。明日出掛けるぞ」
「……明日?」
出迎える間もなく、急な話に驚く。機嫌は悪くなさそうだ。――勘違いだったかな。そう思いながら胸を撫でおろした。
「どこかに視察?」
「違えよ。休暇だ」
「……休暇」
本当に急な話である。
「明日朝一で出発するから、準備しとけよな」
「え、私も行くの?」
「だから休暇だって言ってるだろうが。旅行だよ。当たり前だろ」
急なことで戸惑いはあるものの、旅行と聞いて心が浮き立つ。仲謀とゆっくり過ごせるのも久しぶりな気がした。今日一日、何とはなしに塞いでいた気持ちが晴れていく。
「どこに行くの?」
「山だ」
――すごくアバウトだ。山だけではわからない、と文句を言おうとする前に、仲謀はじゃあなと踵を返して部屋を出ていこうとする。
「用意しとけよ」
「え、寝ないの?」
「執務があるんだよ」
お前は早く寝ろ、と言い残して部屋を出ていってしまった。……今から仕事?それは、明日からの休暇のせいなのだろうか。
すっかり目が覚めてしまい、ほとんどやることのない準備が終わって床についた後も、中々寝付けなかった。結局、仲謀が部屋に帰ってくることはなかった。
不規則に揺れる馬車の中で、欠伸をかみ殺す。寝不足だ。四方を布で囲った馬車は居住性が高く、時折大きく揺れて柱に頭をぶつける以外は快適である。とはいえ――。花よりももっと寝不足であろう仲謀は、そこに報告者や資料を持ち込み、仕事をしていた。
「……大丈夫?」
「何がだよ」
仲謀の視線は手元のまま、花を見ずに返事をする。
「そんなに忙しいのに休暇って――。休むことを休暇って言うんだよ?」
今現在仕事をしていたら、これは休暇とは言えないのではないか。仕事が忙しいことは仕方がないと思うが、休みだ旅行だと言うなら、こんなに忙しそうな時を選ばなくても……と思ってしまう。大体、揺れがある場所で文字を読んだりして、酔ったりしないのだろうか。目の前でこうも根を詰められると、心配になってくる。
「んなことぐらい知ってる」
「そもそも、何で急に決まったの?」
「色々あるんだよ。――天気も問題なかったし」
「天気?」
「まあ、都合も良かったしな」
仲謀は足を組み替えついでに身体を伸ばしながら、そこでやっと花の方を見た。
「俺が公瑾に任せて城を空ければ、同盟反対派の連中も少しは落ち着くだろ。あと、本当に急に決めたから、どこかに何かされる心配も少ないしな」
公瑾の『療養』という名の謹慎が解けてから、まだほんの一月程度。いわば中原制覇のために起こした彼の行動は、玄徳軍との同盟を反対する派閥に大いに支持される結果となっていた。表向きは『怪我の療養』。それも事実ではあったが、仲謀個人の公瑾への思いはどうであれ、彼の処分如何によっては豪族達の反発が起きかねない。その対応に追われていたのは知っている。そして、それは現在進行形なのだろう。公瑾が変わらず仲謀の右腕であることを示すのに、今回は最適だったということか。
旅行一つとっても、襲撃される可能性を考えなくてはならない。偉い人とは大変なものだという考えがよぎるが、もう他人事では済まされないのだと思い直す。とはいえ、花の方も最近は忙しい日々が続いていたため、――目の前の夫は忙しそうな夫はともかく――ちょうど良かったのかもしれない。
「山に行くんだよね」
「ああ。まあ半日もあれば着くし、のんびりできるぞ。温泉もあるしな」
「温泉」
いつぞやの騒動は忘れ、単純なもので気持ちが上向いてくる。と、仲謀が大きな欠伸をした。
「――寝てないんでしょ」
「そうでもしないと時間作れなかったからな」
と言いながらも書簡から目を離そうとしないものだから、楽しみになってきた気持ちに水を差されるような気持ちになる。
「少し寝たら?」
「馬車で寝れるか」
「……じゃあ、膝貸してあげる」
「…………は?」
しっかり聞こえていた証拠に、彼は口をぽかんと開けてその動作を止めてしまった。
「――だから、膝貸してあげるから寝たらいいよ」
要は膝枕なのだが、言い出した方がそわそわと落ち着かなくなる。仲謀はというと、まだ固まっていた。が、徐々にぎこちなく動き出す。
「……別にいい」
「……意地張ってないで寝ればいいじゃん」
「張ってねえ」
目を逸らしながら不機嫌そうに答えだす夫に、先に痺れを切らしたのは花だった。実力行使とばかりに書簡を取り上げてしまう。
「もうこれはおしまい」
「おい、何すんだよ」
「着いてから眠くなるより今寝て欲しいの。ご飯とか温泉とか色々、休むために行くんでしょ?なら今も休んで!」
「……っ」
ふい、と顔を背けた仲謀に、これでも駄目かと苛々が募ってくる。本当頑固なんだから――。自分のことは棚にあげながら、一呼吸ついて、静かに言った。
「……寝るのに膝貸してあげるって言ってるだけなのに。変なこと考えてるから、寝れないんでしょ」
効果はてきめんだった。
「ふっざけんな!馬鹿かお前!寝れるに決まってんだろ‼」
「じゃあ、はい」
顔を真っ赤にしながら抗議する仲謀を無視して、膝を叩いて誘導する。ぐっと詰まる仲謀に、自分だって恥ずかしくないわけではないのに、と心の中で呟いた。
時間にしてたっぷり十秒ほど。観念したのかやっと膝に頭を置いた。横を向いているので顔は見えないが、綺麗な形の耳は心なしか赤い。それに気づくと、先ほどまでのやりとりの苛々も忘れてくすりと笑ってしまった。そしてごく自然に金色の柔らかい髪を撫でると、仲謀が飛び跳ねるようにこちらを見た。
「な、んだよ!」
「撫でただけだよ」
「いらねえよ、子どもじゃねえんだから!」
「……知らない。私が触りたいから触るの。もう寝て」
ぐい、と仲謀の頭を膝に押し戻して、再び髪を撫でる。初めて触った時から柔らかい髪だと思っていたけれど、こうして撫でていると滑らかで気持ちが良い。
最初こそ身体に力が入っていた仲謀も、気が付くと頭の重みが増し、徐々に寝息が聞こえ始めてきた。
寝たかな。
不規則な揺れと、仲謀の寝息、膝の温かさに自分まで眠くなる。
無理をしないで欲しいのに――。そう思いながら、花もいつの間にか意識を手放していた。
******
「おい、着くぞ」
仲謀に揺り起こされて、目が覚める。一瞬、見慣れない場所で驚いたが、そうだ馬車に乗って旅行に出かけていたのだったと思い出す。仲謀に膝枕をして、そのまま寝て――。徐々に思い出す記憶とは裏腹に、足は痺れていなかった。
「……いつから起きてたの?」
「お前と違ってどこでも寝れないんだよ」
「……寝てたよね」
「ああ?」
心なしか目を逸らされている気がするが、追及する前に馬車が止まった。外で使用人達が動き回る気配がする。
天幕が開けられ、眩しさに目を細めた。仲謀に手を引かれて外に出ると、太陽は真上から南へ進み始め、もう昼を過ぎようとしているところだった。さすがに歩くよりも遥かに楽であるとはいえ、長時間同じ姿勢だと体中が痛い。はしたなくない程度に軽く伸びをしていると、立派な建物が目に入った。
「――すごいね」
山の中にこんな建物があるのか、と純粋に驚く。
「子どもの頃に、よく来てたんだぜ」
横に立った仲謀が、嬉しそうに話す。孫家の別荘みたいなものなのだろうか?彼にとって懐かしい場所なのだろう。
日差しのわりに、京に居る時よりも心なしか涼しく、避暑地として扱われているのだろうかと推測する。そこへ身分の高そうな年配の男性に挨拶をされ、建物の中へと導かれた。聞き覚えのある名前だ。確か、孫家と関係の深い豪族の一人だったように思う。どうも話から察するに、この建物は男性の持ち物で仲謀を招いた、という形になるようだった。聞きたそうな気配を察したのか、仲謀が「親父の戦友だった人だ」と教えてくれた。現代の常識では馴染みのない関係が、そこかしらに落ちていると改めて思う。
中は外観同様凝った造りで、掃除の行き届いた素敵な場所だった。
「落ち着いたら少し散策でもするか」
「うん」
部屋に着いてまた仕事を始めるのでは――という懸念が杞憂に終わり、本当に旅行に来たのだなという実感が湧いてくる。
山といえば、この世界に来た時と、過去に飛ばされた時以来だ。今回はゆっくりと景色を楽しみながら散策できることが、何だか新鮮ではある。野花や木の実など、仲謀は色んなことを知っているのだなと今更な発見もあった。
「伯符兄上に戦や剣術は敵わなかったけどな、虫取りでは負けたことがないんだ」
「へえ」
見たことのない色の蜻蛉を見かけ、仲謀の思い出話になった。確かにこの山なら色んな虫が捕まえられそうだな、と思う。
「お前、虫は平気だよな」
「うん。まあ。弟と捕まえたりしてたし」
よく一緒にやってたよ。小さく痛む胸を無視して、笑った。
「勝負でもするか?」
「……遠慮しとく」
敵前逃亡か、とご機嫌な仲謀に、勝てるわけないよねと返す。住宅街で育った私と、山のことをよく知っている仲謀とで勝負になるわけがない。ふと、饒舌な仲謀を見ながら考え込む。
――あの時は怒ってばかりで、こんな話もしなかったな。
出会って間もなかった頃のこと。変わらないもの、変わったもの。どちらもあると思う。それらが嬉しくて愛おしいと思えるのは、この人のことが好きだからなのだろう。
結局、あまり奥に行くと獣も多くなり危ないとのことで、近くの沢や開けた場所から見渡せる益州を見て過ごした。
部屋に戻っても窓から見える緑は美しく、ただここにいるだけでも楽しめるのではないかと思うぐらいであった。この世界にいることが非日常のように感じていたが、嫁ぐことになってからはほぼ城の中にいることが多く、もうそちらの方が日常になってしまったのだなと思う。肌を撫でる風も柔らかく感じ、連れて来てもらえて良かったと喜びに浸っていた。
「ご飯食べる前に、温泉行ってきてもいい?」
「ああ、ゆっくりしてきていいぞ」
言うなり書簡を広げる仲謀に、やはりかと溜息を洩らしたかったが、こればかりは仕方がない。散策に付き合ってくれただけでもよしとしなければいけないのだろう。普段は執務室に籠っているものだから、実際に仕事をする場に同席しているわけではない。見えないものが見えているだけなのだ。
それはそうと、忙しい合間を縫ってここまで来たのは、花のためであることは明らかだ。嬉しい気持ちと、そこまでしなくても、という気持ちがないまぜになる。――そういえば、何故ここに来たのか理由を聞いてなかった。
聞いてみようかとも思ったが、真剣な顔で勤しんでいる姿を見てやめる。私は私で楽しもう。使用人を連れて温泉へと向かった。
露天風呂は簡単な囲いがあるだけで、まだ明るい時間ということもあり、入るのは中々勇気がいった。だが、一度入ってしまえば湯の中だし周囲の様子も気にならないはず。そもそも使用人が見張ってくれているのだし、心配することなどないと割り切った。
足からそっと湯に入る。少し熱いぐらいのお湯に肩まで浸かりきると、体中の力が抜けるようだった。温泉は、元の世界との数少ない共通点だ。
現代で最後に温泉に行ったのはいつだったか。思い出そうとして、頭を振ってやめた。それを知って何になるというのだろう。
無意識に、溜息が零れた。
『楽しい』の裏側に、いつも『寂しい』がひっそりとくっついている気がする。もう戻れないこと、家族や友達に会えないこと。それらは、帰ろうとしていた頃は気にならなかったのに、ここに残ることを決めた後では、思い出す度に胸の奥をじわじわと浸食していくものへと変わってしまった。
忘れたくない。でも、思い出したくない。仕方のないことだとわかっていても、相反する気持ちにバランスが崩れそうになることがある。
こうして元の世界を想い、その度にこの世界が大事だと確認して。これを何度繰り返すのだろう。
――この痛みだけは、これからも抱えていくことになるのだろうか。
「奥方様」
「は、はい!」
急にかけられた声に、びくりと肩を震わせる。水面がぱしゃりと音を立てた。
「のぼせてしまいますから、そろそろ――」
思わず考え込んでしまった。――やはり、現代と似通ったものは妙な感傷を誘ってしまう。湯から上がりながら、頬をぱちぱちと叩いて、余計な思考を落とそうとした。
部屋へ戻ると、予想通り仲謀は部屋を出たときと同じように仕事をしていた。
「仲謀も今から行く?」
「いや、もう食事が来る頃だから、後でいい」
「そっか」
湯上りの火照った身体を涼ませようと、窓際へ座った。陽が稜線との境を滲ませながら沈もうとしていた。夕暮れ時の少し冷えた心地良い風が、部屋の中へ吹き込んでくる。途端、リン、と涼やかな幻聴が聞こえた。――ああ、風鈴が欲しいな。五感に染み付いた季節は、そうそう変えられるものではないらしい。
――どうも、いつもより調子が狂って仕方がない。再び重苦しいしこりが、花の気持ちを沈めようとしてくる。
別のことを考えようと頭を振ると、仲謀が視界に入った。時折唸っているのは、頭を悩ませる事案だからだろうか。
ただ単に気分を変えるのであれば、部屋を出れば良かったのかもしれない。けれど、気が付いた時には仲謀の横に座っていた。
「……どうした」
「……うん」
いつもは座らない距離に、仲謀が訝しむ。
胸に巣食う淀みはじりじりと形を変えているような気すらした。すぐ消える時もあるというのに。
横を向けば、仲謀も花を見ていた。
「何かあったか」
再び聞かれて、話すべきではないか、と悩んでいた心が大きく揺れる。
ほんの少し前のこと。同じように郷愁に駆られて苦しくなった時に、仲謀が言った言葉を思い出す。帰りたいと思う気持ちは悪くない。寂しくなるのも。――そういう時は言えと、この人は言ってくれた。なら――。
手をついてずるずると仲謀の前まで移動する。
「……?」
「抱き着いていい?」
「っ、はあ⁉」
カタン、と書簡が落ちて、横に積んでいた山が崩れた。
「――お、前なあ!飯が来るって言ったの聞いてなかったのかよ!」
「……聞いてたよ。でも――」
少し、ためらう。本当に、言ってもいいのだろうか。この人に余計なことを背負わせてしまわないだろうか。でも悩んだのは一瞬だった。
「辛いときは……、言えって、言った」
「……何か辛いのかよ」
戸惑うように揺れる仲謀の言葉にこくりと頷く。大きく息を吐いてから抱きしめられた。
「そういう時は、わざわざ許可取らないで、さっさと抱き着けばいいだろ」
「……でも怒るよね」
「怒らねえよ」
いや絶対怒ると思う。大体、今聞いたときに怒ったくせに――。そんなことを考えながら、仲謀の背中に手を回す。湯上りで火照った身体が、仲謀の体温に馴染んでいく。
「――何が辛いんだよ」
「……何て言ったらいいか、わからないの」
話した方がいいのか、話さない方がいいのか。こればかりは、どうしようもないのだ。ただ、通り過ぎるのを待つしかない。それでも、辛いのだと伝えることを選んでしまった。
「じゃあ、言えそうになったら言え」
待っててやるから。
まっすぐ、そうあっさりと返された仲謀の言葉が、静かに染み渡っていく。たった、それだけなのに。喉元につかえていたような息苦しさが引いていくのがわかった。
「……大丈夫になった」
「は?」
「辛いの、なくなっちゃった」
「……いや、早すぎだろ。本当に大丈夫なのかよ」
困惑する仲謀に、ふふ、と笑う。すごい。本当に治ってしまった。
「……大丈夫ならいいけどよ」
「うん。……大丈夫なんだけどね――」
ものすごく居心地の良い場所を見つけた猫の気分とは、こんなものだろうかと想像する。
「もうちょっと、このままでもいい?」
「…………」
「仲謀?」
ものすごく大きな溜息が聞こえたかと思うと、抱きしめられていた腕が解かれる。
「――お前は本当に時と場所を考慮しろ。今すぐ改めろ」
「……何の話?」
「怒ってんだよ俺は‼」
「……ちゃんと考えてるよ」
「人前じゃなきゃいいって話じゃないからな⁉」
「……つまり、離れろってこと?」
「…………お前は離れなくていい」
何かと葛藤したらしい長い間があった。私だけ抱き着いていろということだろうか。
「……よくわかんないけど」
とん、と再度仲謀の胸に頭を預ける。
「仲謀はすぐ怒る」
「だから!お前のせいなんだよ!」
怒る仲謀を無視しながら、食事の用意が出来たと外から声をかけられるまで、ずっとそのままでいた。
夕餉は京城で出るものとはやはり違っていて、仲謀の説明を聞きながら楽しく食べ終えた。山には山の、海には海の宝ともいうべき、その場所にしかない食材やものがあることを強く実感する。もう明日の朝にはここを発つ。急だったけれど、本当に楽しい旅行だったなと反芻しながら、仲謀に声をかけた。
「仲謀、お風呂は?」
「ああ、後で。ちょっと出かけるぞ」
「今から?」
「今からだよ」
予想外の言葉に首を傾げながらも、外は冷えるからと一枚余分に羽織らせられた。
手を引かれて外に出ると、昼間とは違って木々の茂りは暗く、怖くすらあった。お付きの者が数人ついてきているというが、姿は見えない。
生憎、三日月のせいで灯りも乏しい。足元を照らすのは仲謀が持っている提灯のみだ。
「……どこまで行くの?」
「もう少しだ」
梟か何かの声が森中に響き渡る。少し離れた場所でガサリと音が鳴ると、反射的に身体が震えてしまう。
「何だ、怖いのかよ」
「……当たり前だよ」
「俺様がいるんだから余計な心配すんな」
「…………」
単純なもので、そう言われた途端不安が薄れていくのがわかった。何だか悔しくて、返事の代わりに握った手に力を込める。先ほどまでは気が付かなかった夏の虫の鳴き声が、柔らかに辺りに反響する。そして少し坂を上り、樹木がない開けた場所に出た時のことだった。
「ほら、着いたぞ」
仲謀に導かれるまま辿り着いたその光景に、ただただ声を失った。
「―――――」
空いっぱい。真っ白とも言えるほどの星が散りばめられていた。すごく遠くにあるはずなのに、今にも星が落ちてきそうだ。星が瞬く度に音がしているような気さえする。ただそこに静かに存在しているだけなのに、圧倒的な光景は五感全てに訴えかけるようものを持っているようだ。
「すごいだろ」
「…………」
本当に、すごい。
住んでいた場所は元より、山に旅行へ出かけたことだってある。その時に綺麗な星空を見た気がしなくもないが、こんな星空は初めてだった。
「これを見せてやりたかったんだよ」
優しい仲謀の声に、また返事の代わりに手を握りしめた。何だか泣きそうで、唇を軽く噛みしめる。
「……ありがとう」
胸がいっぱいで、お礼を言うことしかできない。息苦しいほどの美しさに、しばらく溺れるように見入っていた。
身体が冷える前に帰ろう、と言われて、夢心地のまま手を引かれて歩き出す。
この世のものではないと思うぐらい、美しいものを見たからだろうか。タガが外れているのか、今なら言える気がした。
「……仲謀」
「なんだよ」
「……弟の話、していい?」
前を歩いている仲謀の顔は見えない。が、握った手に力が籠ったのがわかった。仲謀にとって聞きたい話なのかはわからない。それでも、言いたいと思った。
「……ああ」
「黄巾党の時代に飛んじゃった時のこと、覚えてる?」
「はあ?あ、ああ」
仲謀は思わぬ話題に面食らったようで、声が揺れる。
「仲謀と話しながらね、弟のこと思い出してた」
「……そうか」
「機嫌が悪くなると黙るとことか、弟みたいだなって」
「……お前、俺が年下なのを気にしてんの知ってて、それ言うか?」
「え、気にしてたの?」
「……もういい。で?」
疲れたような諦めた声音に促され、伝えたかったことを思い浮かべる。周囲は暗く、前を歩いているから仲謀の表情は見えない。見えなくて良かったと少し思う。暗がりが怖かった行きとは違う意味で、心臓がどきどきしている。
「……生意気な子なんだけど、年が離れてるから、あまり喧嘩とかはしたことなくて。わがままだし、どうせ私なら言うこと聞いてくれるだろう、って無理難題言うし。……でもね、姉ちゃんって頼られるの嬉しかった」
唐突に、涙が一粒だけ溢れた。
「大好きだった。大切で――」
たった一人の弟。
なのに、何故だろう。思い出そうとすると、酷く曖昧なことしか出てこない。もっと、弟がどんな子で、こういう良いところがあるんだとか、具体的に話そうと思っていたのに。仲謀に、知っていて欲しかった。私の大事な家族のことを――。なのに、一瞬一瞬を写真で切り取ったような表情が、ぱらぱらと浮かんでは消えていく。
どうやっても、これ以上弟について話すことが出来そうになかった。私は、弟に対する思い出も、言葉も、もうこれ以上持っていない。そして、それは母親と父親についても同じだろうと思った。
こうやって消えていくものなのだろうか。それとも、今まで話すことを避けていたから、忘れてしまったのだろうか。どちらにしろ、涙は最初の一粒しか流れなかったし、話すことが出来ない事実に対して、自分でも驚くほど悲しさは感じなかった。
急に、仲謀が立ち止まった。少し躊躇ったような間の後、振り返って少し驚いた顔をする。
「――泣いてんのかと思った」
涙の跡も残さなかった頬をゆっくりと撫でられた。その手を上からそっと握る。――何故悲しくないのか、わかった。
「……良かった」
「――何がだよ」
消えていく記憶が、仲謀ではなくて。
薄情だと思う。十七年過ごした場所、血の繋がった家族よりも、目の前にいる人の方が大事などと。帰らなかった後悔はまだ疼くけれど、苦しい時は仲謀がいれば治ってしまうことも知ってしまった。
今、私はこの人を忘れるぐらいなら、帰らなくて良かったと心から思ってしまった。
「……聞いてくれてありがとう。帰ろう」
釈然としないような仲謀の顔。いや、違う。不安そうな顔だ。ちゃんと言わなくてはいけない。
「私ね、ここに残って良かった。仲謀と、ずっと一緒に居たい」
他の何を捨ててでも、私は仲謀のことだけは諦められないんだ。
******
突然の休暇はあっという間に終わり、もう帰路に向かう馬車の中だ。風通し用に開けられた幕の隙間からは気持ちの良い風が入り込んでくるし、揺れは心地良いしで、欠伸が抑えられない。
仲謀はというと、ぼうっと外を眺めていた。
「お仕事はもう終わったの?」
「終わってねえ」
「……大丈夫なの?」
頑張りすぎていても心配だし、終わってないと聞くとそれはそれで心配だ。どことなく、いつもと様子が違う気もしていた。
「ま、少しくらい多めに見てくれるだろ」
仲謀は頭の後ろで腕を組んで、身体を伸ばした。今回の休暇を取るにあたり、相当無理をしたのだろうが、何故今だったのかを聞きそびれていた。
「都合が良いって言ってたけど……。何かきっかけでもあったの?」
「――別に」
頬杖をついて、じっと見つめられた。
「お前は……」
「?」
言い淀む仲謀に首を傾げる。
「楽しかったか?」
「うん。すごく楽しかった。連れて来てくれてありがとう」
「――そ、っか。またいつでも連れて来てやるよ」
「……うん」
いつでも。先の約束が出来ることが嬉しい。湧き上がる気持ちをそのまま伝えることが出来たらいいのに。
「また行きたい」
その言葉に、仲謀がやっと小さく笑った。途端、外で馬のいななきが響き渡る。何かあったのだろうか。そちらに気を取られていると、仲謀が小さく呟く声が聞こえた。
「? 何か言った?」
「いや、何でもねえ」
どこか吹っ切れたような表情で、笑いかけられる。
「仲謀様」
外からお付きの人が声をかけてきた。どうも先行していた馬車の車輪が道を外れてしまったらしく、対処中だという報告だった。
「ま、帰ったらまた仕事漬けだろうし、帰りぐらいゆっくりする」
「そうだね」
何を言っていたのか聞きそびれたことも忘れ、他愛のない話を再開する。
ようやく馬車も動き出し会話もなくなると、車輪が地面を踏みしめる音と、馬蹄が地面を蹴る音がやけに大きく聞こえた。外にいる兵士達が楽しそうに笑う声も。
周囲の音に耳を澄ませていると、本格的に睡魔が襲ってきた。
「寝とけ。まだしばらくかかる」
「……うん」
見ていないようで、花の様子は把握している。その安心感に、言われるまま素直に目を閉じた。
城に着くとすぐに大喬や小喬、尚香達が出迎えてくれた。離れていたのはほんの一日半だったというのに、何だかすごく久しぶりな気がする。お土産を渡して喜ぶ顔を見てから、仲謀は執務室へ直行し、花は休むために部屋へと向かった。あれだけ寝たというのに、いや寧ろ寝すぎたせいなのかまだ眠気が取れていなかった。
旅行は楽しかったものの、帰ってくるとそれはそれで安心する。それだけ、ここが自分にとって当たり前の場所になっているのだろうと思うと、嬉しかった。
そんなことを考えていると、廊下の向こうから公瑾がこちらへ歩いていくのが見えた。目が合う。
「――これは奥方様。お帰りなさいませ」
「た、ただいま帰りました……」
花の目下の課題は、公瑾とどう付き合うか……である。ここに至るまでに自分のことをよく思われていないのは明白だった。復帰してからは、少し物腰が柔らかくなったように思えなくもないが――。
「お祝いは楽しめましたか?」
「……お祝い?」
急に振られた話題に首を傾げる。何のことだろう。
答えられないでいると、公瑾が眉根を寄せた。
「――お祝いで行かれたのでしょう?」
「え、っと……?」
「…………」
沈黙が続いた後、公瑾が大きな溜息を吐いた。
「……奥方様」
「は、はい」
凛とした声で急に呼ばれ、背筋が伸びる。
「今の、聞かなかったことにして頂けますか?」
「へ?」
何を言われているのか飲み込めないでいると、公瑾が今まで見た中でも、とびきりの笑みを浮かべた。
「して頂けますか?」
「……はい」
彼は強めに私にお願いした後、袖で口元を隠しながら小さくぼやいた。
「――まったく、しょうがない人ですね」
何のことだろう。当然聞く勇気はなく、聞こえない振りをした。
「では、私はこれで」
「あ、はい」
ろくに会話も出来ないまま、いつも通りの涼し気な雰囲気で去っていく公瑾の背中を見る。
――お祝い?
聞かなかったことに、と言われて都合よく忘れられるわけがなく、歩きながら考える。
最近の出来事といえば、旅行しか思い当たることがない。旅行がお祝いだったということだろうか。何か祝うことなんて――。
たどり着いた答えに、思わず足が止まった。
――誕生日?
『色々あるんだよ。――天気も問題なかったし』
『これを見せてやりたかったんだよ』
『――別に』
仲謀の言葉が線を繋ぐように蘇り、胸が締め付けられた。何故、無理を通してでも出かけたのか。結局彼は理由を言わなかった。
肝心なことは、いつも言ってくれない。どんな気持ちであの場所に連れて行ってくれたんだろう。どうして、私ばかり楽にさせるのだろう。仲謀の、不安そうな顔を思い出した。
――寄りかかっているばかりだと、何も見えない。
「……ばかだなあ」
行き場のない感情が苦しいぐらい溢れて、衣の裾を掴んでやりきる。
さっきまでずっと一緒だったのに、どうしようもなく貴方に会いたい。
webオンリー用に、本来書きたかったものの後日談として書きました。そっちの方はまだ完成していませんが必ず完成させます。
拙さ全開で書き直したいものの、一番見て頂いたものなのでそのままにしています。
****************
どこまでも濃い青空が窓から見える。蝉の声に、大きな入道雲。この世界に来て初めての夏は後半に向かっていた。汗はともかく、入り込んでくる夏の気配は心地良い。食後のお茶を用意していた年配の使用人が、にこにこと話し出した。
「そういえば、仲謀様がお生まれになった時も、こんな陽気でしたねえ」
「……仲謀って夏生まれなんですか?」
「ええ。とても天気のよい日でしたよ」
懐かしそうに目元を綻ばせて、仲謀に笑いかける。
「本当に大きく立派になられて」
「――それはもういい」
ややうんざりした様に仲謀が返す。恥ずかしいならそう言えばいいのに。たまに来るこの使用人は、元々は呉夫人に仕えていたらしく、度々思い出話をしては仲謀を照れさせていた。仕事を終えた彼女は、くすくすと笑いながら一礼をして退室していく。
「そっか、夏なんだ」
すごく『ぽいなあ』と思った。夏の日差しに反射する彼の金の髪は綺麗だから。
「もう過ぎてるけどな」
「そうなの?」
こちらでは誕生日を当日に祝ったりしないのだろうか。疑問に思って聞いてみると、どうやら生まれた日ではなく、年を取るのも贈り物をするのも、年明けに行う習慣らしい。
「私の世界だと、生まれた日が特別で、その日に年を取るんだ」
そういえば、昔は年齢の数え方が違った、という話を聞いたことがあるかもしれない。そもそも国自体が違うわけだし――と考え込んでいると、仲謀がじっとこちらを見ていることに気がついた。
「……特別って何かするのか?」
「誕生日?そうだね――」
ふと、よぎった記憶に思わず言い淀む。
「……え、と。御馳走食べたり、とか。プレゼントも」
今年のプレゼントは、ゲームだった。ごちそうを作らなきゃと張り切る母に頼まれた、弟の誕生日プレゼント。タイトルは携帯にメモしていたから、もう思い出すこともない。誕生日にいなくなった姉を、家族はどう思っているのだろう――。
「ぷれぜんと?」
不思議そうに聞き返す仲謀の声に、現実に引き戻される。
「あ、贈り物のことだよ」
「……へえ。あまりこっちと変わらないんだな」
「そう、だね」
変わらないのだろうか。今までこの世界に過ごしてきた中で、元の世界と変わらないものはあまり見当たらない。お祝い一つとってみても、やはり馴染みのない儀式的なものが多く、同じとは言い難いのではないかと思う。
「――お前は」
「?」
「いつなんだ?生まれた日は」
「私?春だよ」
もうとっくに過ぎていることを伝えると、仲謀が眉根を寄せた。
「何で言わねえんだよ」
「……え、何でって。私も忘れてたし。仲謀だって言わなかったじゃない」
正直、誕生日当日にあまり意味がないことを知って、ほっとしていた。自分が生まれた日という、どうやっても元の世界に残してきた家族と直結することを、考えられる余裕は自分にはまだない。胸の辺りに巣食った罪悪感という名のしこりが痛むのだ。
ふと、仲謀を見ると怒ったような顔で黙り込んでいた。
「……どうしたの?」
「……何でもねえ」
そう言って立ち上がると、上着を着始めてしまう。
「もう行くの?」
「ああ」
「……いってらっしゃい」
――さっきまで機嫌悪そうじゃなかったのに。出会ったときよりはわかることも増えたけれど、未だに仲謀の機嫌のスイッチは不明な部分がある。振り返りもせず戸を閉めた仲謀の背中を思い出して、無意識に溜息を吐いた。
******
「おい、公瑾。いるか」
「仲謀様――。今からお伺いしようかと。何か急ぎの用でも?」
朝議よりも前に突然執務室に現れた主と話すため、書簡から目を上げた。難しい顔をしていた主を見て、何か良くない報せでも、と思わず身構える。
「祝うのに何をやったら喜ぶと思う」
「……は?」
予想外すぎる問いかけに思考が停止しそうになりながらも、とりあえず笑みを浮かべた。おそらく執務とは全然関係のない話だ。
「……奥方様のことでしょうか」
「そうだ」
――何故、私に聞くのだろう。軽い眩暈を覚えながら、何かめでたいことでも?と尋ねる。
「花が生まれた日を祝う。もう過ぎてるが」
――尚更、何故私に。そもそもそれは年明けに行うことが常であるし、今必要なことなのだろうか。思わず片手で顔を覆いながら、非常に面倒なことに巻き込まれているのでは?という疑念が浮かんでくる。
「そう、ですね……。女人への贈り物でしたら、定番は玉で――」
「あいつが喜ぶと思うか?」
「……いいえ」
普段の服装からして、華美なものを好むとは思えない。
「では、食べ物など」
「それは別に用意する」
即座に否定される。
「――何がいいのでしょうね」
至極どうでもいい。とりあえず山積みの仕事に目を向けて欲しい――。そんなことを考えながら仲謀を見ると、腕を組んで真剣な顔をして考え込んでいた。
その姿が公瑾の記憶の琴線に引っかかった。そして、糸を手繰り寄せてたどり着いた答えに、吐息が漏れる。避けていたとでも言うべき懐かしい情景の一つが蘇ってしまった。
「……時間はどうでしょうか」
「時間?」
「最近仲謀様はお忙しいですから――。お二人で出掛ける等、ゆっくり過ごされては如何ですか?」
執務の方は頑張って頂ければ埋め合わせもできましょう。
「……そうだな。そうする。邪魔したな」
納得した様子にこれで仕事も片付くだろう、と胸を撫でおろした時だった。
「やっぱりお前に聞いて良かった」
そう言い残して、彼は部屋を出て行った。
徐々に遠のいていく足音。静まり返った部屋の中で、頭の中には先ほど蘇ってしまった懐かしい声が響いている。
『兄上が喜ぶものは何でしょうか』
『だって、公瑾は兄上と一番仲が良いから』
『あと――』
思わず天を仰ぎ見る。そんなこともあった。珍しく後悔以外の念で昔を思い出した気がする。
『公瑾なら、必ず答えをくれると思って』
「……何故」
時を経て、昔と同じものなんてないと思っていたのに。
「変わらないんでしょうね、仲謀様は……」
揺るぎないその信頼は何なのだろう。それなのに、もたれ掛かるのではなく、自分の足でしっかりと自分の足で歩いていく。
『あいつは馬鹿正直でまっすぐだから、人の話をちゃんと聞くだろう。そうすると周りが放っておかない。――なあ、俺が頼まなくたって、お前はあいつのこと助けてやるだろ』
弟の才について嬉しそうに語る親友のことまで思い出してしまった。
仲謀の、『他者を切り捨てられない』あの優しさは乱世では危ういものだと、ずっと思っていた。だが、治世において、それは弱点にはならないのかもしれない。最近は、そう考えるようになっていた。
「――お前の言う通りだな」
ぽつりと漏らした言葉は、風に吹かれて消えていった。
******
仲謀が怒ったように出て行ったその日。夕食時も部屋には戻ってこず、執務室に籠りきりのようだった。それとなく使用人に尋ねると、「そういえば、今日はお忙しいようで姿を見ていませんね……」と返ってきた。いつもより忙しいのは間違いなさそうだった。
やはり何か怒っていたのだろうか。話がしたかったのだけれど、と無意識に溜息を零してしまう。とはいえ、夜も深まりいつ帰ってくるかわからない。そろそろ寝ようと立ち上がった時、やっと仲謀が帰ってきた。
「おかえ――」
「何だ起きてたのかよ。――丁度良かった。明日出掛けるぞ」
「……明日?」
出迎える間もなく、急な話に驚く。機嫌は悪くなさそうだ。――勘違いだったかな。そう思いながら胸を撫でおろした。
「どこかに視察?」
「違えよ。休暇だ」
「……休暇」
本当に急な話である。
「明日朝一で出発するから、準備しとけよな」
「え、私も行くの?」
「だから休暇だって言ってるだろうが。旅行だよ。当たり前だろ」
急なことで戸惑いはあるものの、旅行と聞いて心が浮き立つ。仲謀とゆっくり過ごせるのも久しぶりな気がした。今日一日、何とはなしに塞いでいた気持ちが晴れていく。
「どこに行くの?」
「山だ」
――すごくアバウトだ。山だけではわからない、と文句を言おうとする前に、仲謀はじゃあなと踵を返して部屋を出ていこうとする。
「用意しとけよ」
「え、寝ないの?」
「執務があるんだよ」
お前は早く寝ろ、と言い残して部屋を出ていってしまった。……今から仕事?それは、明日からの休暇のせいなのだろうか。
すっかり目が覚めてしまい、ほとんどやることのない準備が終わって床についた後も、中々寝付けなかった。結局、仲謀が部屋に帰ってくることはなかった。
不規則に揺れる馬車の中で、欠伸をかみ殺す。寝不足だ。四方を布で囲った馬車は居住性が高く、時折大きく揺れて柱に頭をぶつける以外は快適である。とはいえ――。花よりももっと寝不足であろう仲謀は、そこに報告者や資料を持ち込み、仕事をしていた。
「……大丈夫?」
「何がだよ」
仲謀の視線は手元のまま、花を見ずに返事をする。
「そんなに忙しいのに休暇って――。休むことを休暇って言うんだよ?」
今現在仕事をしていたら、これは休暇とは言えないのではないか。仕事が忙しいことは仕方がないと思うが、休みだ旅行だと言うなら、こんなに忙しそうな時を選ばなくても……と思ってしまう。大体、揺れがある場所で文字を読んだりして、酔ったりしないのだろうか。目の前でこうも根を詰められると、心配になってくる。
「んなことぐらい知ってる」
「そもそも、何で急に決まったの?」
「色々あるんだよ。――天気も問題なかったし」
「天気?」
「まあ、都合も良かったしな」
仲謀は足を組み替えついでに身体を伸ばしながら、そこでやっと花の方を見た。
「俺が公瑾に任せて城を空ければ、同盟反対派の連中も少しは落ち着くだろ。あと、本当に急に決めたから、どこかに何かされる心配も少ないしな」
公瑾の『療養』という名の謹慎が解けてから、まだほんの一月程度。いわば中原制覇のために起こした彼の行動は、玄徳軍との同盟を反対する派閥に大いに支持される結果となっていた。表向きは『怪我の療養』。それも事実ではあったが、仲謀個人の公瑾への思いはどうであれ、彼の処分如何によっては豪族達の反発が起きかねない。その対応に追われていたのは知っている。そして、それは現在進行形なのだろう。公瑾が変わらず仲謀の右腕であることを示すのに、今回は最適だったということか。
旅行一つとっても、襲撃される可能性を考えなくてはならない。偉い人とは大変なものだという考えがよぎるが、もう他人事では済まされないのだと思い直す。とはいえ、花の方も最近は忙しい日々が続いていたため、――目の前の夫は忙しそうな夫はともかく――ちょうど良かったのかもしれない。
「山に行くんだよね」
「ああ。まあ半日もあれば着くし、のんびりできるぞ。温泉もあるしな」
「温泉」
いつぞやの騒動は忘れ、単純なもので気持ちが上向いてくる。と、仲謀が大きな欠伸をした。
「――寝てないんでしょ」
「そうでもしないと時間作れなかったからな」
と言いながらも書簡から目を離そうとしないものだから、楽しみになってきた気持ちに水を差されるような気持ちになる。
「少し寝たら?」
「馬車で寝れるか」
「……じゃあ、膝貸してあげる」
「…………は?」
しっかり聞こえていた証拠に、彼は口をぽかんと開けてその動作を止めてしまった。
「――だから、膝貸してあげるから寝たらいいよ」
要は膝枕なのだが、言い出した方がそわそわと落ち着かなくなる。仲謀はというと、まだ固まっていた。が、徐々にぎこちなく動き出す。
「……別にいい」
「……意地張ってないで寝ればいいじゃん」
「張ってねえ」
目を逸らしながら不機嫌そうに答えだす夫に、先に痺れを切らしたのは花だった。実力行使とばかりに書簡を取り上げてしまう。
「もうこれはおしまい」
「おい、何すんだよ」
「着いてから眠くなるより今寝て欲しいの。ご飯とか温泉とか色々、休むために行くんでしょ?なら今も休んで!」
「……っ」
ふい、と顔を背けた仲謀に、これでも駄目かと苛々が募ってくる。本当頑固なんだから――。自分のことは棚にあげながら、一呼吸ついて、静かに言った。
「……寝るのに膝貸してあげるって言ってるだけなのに。変なこと考えてるから、寝れないんでしょ」
効果はてきめんだった。
「ふっざけんな!馬鹿かお前!寝れるに決まってんだろ‼」
「じゃあ、はい」
顔を真っ赤にしながら抗議する仲謀を無視して、膝を叩いて誘導する。ぐっと詰まる仲謀に、自分だって恥ずかしくないわけではないのに、と心の中で呟いた。
時間にしてたっぷり十秒ほど。観念したのかやっと膝に頭を置いた。横を向いているので顔は見えないが、綺麗な形の耳は心なしか赤い。それに気づくと、先ほどまでのやりとりの苛々も忘れてくすりと笑ってしまった。そしてごく自然に金色の柔らかい髪を撫でると、仲謀が飛び跳ねるようにこちらを見た。
「な、んだよ!」
「撫でただけだよ」
「いらねえよ、子どもじゃねえんだから!」
「……知らない。私が触りたいから触るの。もう寝て」
ぐい、と仲謀の頭を膝に押し戻して、再び髪を撫でる。初めて触った時から柔らかい髪だと思っていたけれど、こうして撫でていると滑らかで気持ちが良い。
最初こそ身体に力が入っていた仲謀も、気が付くと頭の重みが増し、徐々に寝息が聞こえ始めてきた。
寝たかな。
不規則な揺れと、仲謀の寝息、膝の温かさに自分まで眠くなる。
無理をしないで欲しいのに――。そう思いながら、花もいつの間にか意識を手放していた。
******
「おい、着くぞ」
仲謀に揺り起こされて、目が覚める。一瞬、見慣れない場所で驚いたが、そうだ馬車に乗って旅行に出かけていたのだったと思い出す。仲謀に膝枕をして、そのまま寝て――。徐々に思い出す記憶とは裏腹に、足は痺れていなかった。
「……いつから起きてたの?」
「お前と違ってどこでも寝れないんだよ」
「……寝てたよね」
「ああ?」
心なしか目を逸らされている気がするが、追及する前に馬車が止まった。外で使用人達が動き回る気配がする。
天幕が開けられ、眩しさに目を細めた。仲謀に手を引かれて外に出ると、太陽は真上から南へ進み始め、もう昼を過ぎようとしているところだった。さすがに歩くよりも遥かに楽であるとはいえ、長時間同じ姿勢だと体中が痛い。はしたなくない程度に軽く伸びをしていると、立派な建物が目に入った。
「――すごいね」
山の中にこんな建物があるのか、と純粋に驚く。
「子どもの頃に、よく来てたんだぜ」
横に立った仲謀が、嬉しそうに話す。孫家の別荘みたいなものなのだろうか?彼にとって懐かしい場所なのだろう。
日差しのわりに、京に居る時よりも心なしか涼しく、避暑地として扱われているのだろうかと推測する。そこへ身分の高そうな年配の男性に挨拶をされ、建物の中へと導かれた。聞き覚えのある名前だ。確か、孫家と関係の深い豪族の一人だったように思う。どうも話から察するに、この建物は男性の持ち物で仲謀を招いた、という形になるようだった。聞きたそうな気配を察したのか、仲謀が「親父の戦友だった人だ」と教えてくれた。現代の常識では馴染みのない関係が、そこかしらに落ちていると改めて思う。
中は外観同様凝った造りで、掃除の行き届いた素敵な場所だった。
「落ち着いたら少し散策でもするか」
「うん」
部屋に着いてまた仕事を始めるのでは――という懸念が杞憂に終わり、本当に旅行に来たのだなという実感が湧いてくる。
山といえば、この世界に来た時と、過去に飛ばされた時以来だ。今回はゆっくりと景色を楽しみながら散策できることが、何だか新鮮ではある。野花や木の実など、仲謀は色んなことを知っているのだなと今更な発見もあった。
「伯符兄上に戦や剣術は敵わなかったけどな、虫取りでは負けたことがないんだ」
「へえ」
見たことのない色の蜻蛉を見かけ、仲謀の思い出話になった。確かにこの山なら色んな虫が捕まえられそうだな、と思う。
「お前、虫は平気だよな」
「うん。まあ。弟と捕まえたりしてたし」
よく一緒にやってたよ。小さく痛む胸を無視して、笑った。
「勝負でもするか?」
「……遠慮しとく」
敵前逃亡か、とご機嫌な仲謀に、勝てるわけないよねと返す。住宅街で育った私と、山のことをよく知っている仲謀とで勝負になるわけがない。ふと、饒舌な仲謀を見ながら考え込む。
――あの時は怒ってばかりで、こんな話もしなかったな。
出会って間もなかった頃のこと。変わらないもの、変わったもの。どちらもあると思う。それらが嬉しくて愛おしいと思えるのは、この人のことが好きだからなのだろう。
結局、あまり奥に行くと獣も多くなり危ないとのことで、近くの沢や開けた場所から見渡せる益州を見て過ごした。
部屋に戻っても窓から見える緑は美しく、ただここにいるだけでも楽しめるのではないかと思うぐらいであった。この世界にいることが非日常のように感じていたが、嫁ぐことになってからはほぼ城の中にいることが多く、もうそちらの方が日常になってしまったのだなと思う。肌を撫でる風も柔らかく感じ、連れて来てもらえて良かったと喜びに浸っていた。
「ご飯食べる前に、温泉行ってきてもいい?」
「ああ、ゆっくりしてきていいぞ」
言うなり書簡を広げる仲謀に、やはりかと溜息を洩らしたかったが、こればかりは仕方がない。散策に付き合ってくれただけでもよしとしなければいけないのだろう。普段は執務室に籠っているものだから、実際に仕事をする場に同席しているわけではない。見えないものが見えているだけなのだ。
それはそうと、忙しい合間を縫ってここまで来たのは、花のためであることは明らかだ。嬉しい気持ちと、そこまでしなくても、という気持ちがないまぜになる。――そういえば、何故ここに来たのか理由を聞いてなかった。
聞いてみようかとも思ったが、真剣な顔で勤しんでいる姿を見てやめる。私は私で楽しもう。使用人を連れて温泉へと向かった。
露天風呂は簡単な囲いがあるだけで、まだ明るい時間ということもあり、入るのは中々勇気がいった。だが、一度入ってしまえば湯の中だし周囲の様子も気にならないはず。そもそも使用人が見張ってくれているのだし、心配することなどないと割り切った。
足からそっと湯に入る。少し熱いぐらいのお湯に肩まで浸かりきると、体中の力が抜けるようだった。温泉は、元の世界との数少ない共通点だ。
現代で最後に温泉に行ったのはいつだったか。思い出そうとして、頭を振ってやめた。それを知って何になるというのだろう。
無意識に、溜息が零れた。
『楽しい』の裏側に、いつも『寂しい』がひっそりとくっついている気がする。もう戻れないこと、家族や友達に会えないこと。それらは、帰ろうとしていた頃は気にならなかったのに、ここに残ることを決めた後では、思い出す度に胸の奥をじわじわと浸食していくものへと変わってしまった。
忘れたくない。でも、思い出したくない。仕方のないことだとわかっていても、相反する気持ちにバランスが崩れそうになることがある。
こうして元の世界を想い、その度にこの世界が大事だと確認して。これを何度繰り返すのだろう。
――この痛みだけは、これからも抱えていくことになるのだろうか。
「奥方様」
「は、はい!」
急にかけられた声に、びくりと肩を震わせる。水面がぱしゃりと音を立てた。
「のぼせてしまいますから、そろそろ――」
思わず考え込んでしまった。――やはり、現代と似通ったものは妙な感傷を誘ってしまう。湯から上がりながら、頬をぱちぱちと叩いて、余計な思考を落とそうとした。
部屋へ戻ると、予想通り仲謀は部屋を出たときと同じように仕事をしていた。
「仲謀も今から行く?」
「いや、もう食事が来る頃だから、後でいい」
「そっか」
湯上りの火照った身体を涼ませようと、窓際へ座った。陽が稜線との境を滲ませながら沈もうとしていた。夕暮れ時の少し冷えた心地良い風が、部屋の中へ吹き込んでくる。途端、リン、と涼やかな幻聴が聞こえた。――ああ、風鈴が欲しいな。五感に染み付いた季節は、そうそう変えられるものではないらしい。
――どうも、いつもより調子が狂って仕方がない。再び重苦しいしこりが、花の気持ちを沈めようとしてくる。
別のことを考えようと頭を振ると、仲謀が視界に入った。時折唸っているのは、頭を悩ませる事案だからだろうか。
ただ単に気分を変えるのであれば、部屋を出れば良かったのかもしれない。けれど、気が付いた時には仲謀の横に座っていた。
「……どうした」
「……うん」
いつもは座らない距離に、仲謀が訝しむ。
胸に巣食う淀みはじりじりと形を変えているような気すらした。すぐ消える時もあるというのに。
横を向けば、仲謀も花を見ていた。
「何かあったか」
再び聞かれて、話すべきではないか、と悩んでいた心が大きく揺れる。
ほんの少し前のこと。同じように郷愁に駆られて苦しくなった時に、仲謀が言った言葉を思い出す。帰りたいと思う気持ちは悪くない。寂しくなるのも。――そういう時は言えと、この人は言ってくれた。なら――。
手をついてずるずると仲謀の前まで移動する。
「……?」
「抱き着いていい?」
「っ、はあ⁉」
カタン、と書簡が落ちて、横に積んでいた山が崩れた。
「――お、前なあ!飯が来るって言ったの聞いてなかったのかよ!」
「……聞いてたよ。でも――」
少し、ためらう。本当に、言ってもいいのだろうか。この人に余計なことを背負わせてしまわないだろうか。でも悩んだのは一瞬だった。
「辛いときは……、言えって、言った」
「……何か辛いのかよ」
戸惑うように揺れる仲謀の言葉にこくりと頷く。大きく息を吐いてから抱きしめられた。
「そういう時は、わざわざ許可取らないで、さっさと抱き着けばいいだろ」
「……でも怒るよね」
「怒らねえよ」
いや絶対怒ると思う。大体、今聞いたときに怒ったくせに――。そんなことを考えながら、仲謀の背中に手を回す。湯上りで火照った身体が、仲謀の体温に馴染んでいく。
「――何が辛いんだよ」
「……何て言ったらいいか、わからないの」
話した方がいいのか、話さない方がいいのか。こればかりは、どうしようもないのだ。ただ、通り過ぎるのを待つしかない。それでも、辛いのだと伝えることを選んでしまった。
「じゃあ、言えそうになったら言え」
待っててやるから。
まっすぐ、そうあっさりと返された仲謀の言葉が、静かに染み渡っていく。たった、それだけなのに。喉元につかえていたような息苦しさが引いていくのがわかった。
「……大丈夫になった」
「は?」
「辛いの、なくなっちゃった」
「……いや、早すぎだろ。本当に大丈夫なのかよ」
困惑する仲謀に、ふふ、と笑う。すごい。本当に治ってしまった。
「……大丈夫ならいいけどよ」
「うん。……大丈夫なんだけどね――」
ものすごく居心地の良い場所を見つけた猫の気分とは、こんなものだろうかと想像する。
「もうちょっと、このままでもいい?」
「…………」
「仲謀?」
ものすごく大きな溜息が聞こえたかと思うと、抱きしめられていた腕が解かれる。
「――お前は本当に時と場所を考慮しろ。今すぐ改めろ」
「……何の話?」
「怒ってんだよ俺は‼」
「……ちゃんと考えてるよ」
「人前じゃなきゃいいって話じゃないからな⁉」
「……つまり、離れろってこと?」
「…………お前は離れなくていい」
何かと葛藤したらしい長い間があった。私だけ抱き着いていろということだろうか。
「……よくわかんないけど」
とん、と再度仲謀の胸に頭を預ける。
「仲謀はすぐ怒る」
「だから!お前のせいなんだよ!」
怒る仲謀を無視しながら、食事の用意が出来たと外から声をかけられるまで、ずっとそのままでいた。
夕餉は京城で出るものとはやはり違っていて、仲謀の説明を聞きながら楽しく食べ終えた。山には山の、海には海の宝ともいうべき、その場所にしかない食材やものがあることを強く実感する。もう明日の朝にはここを発つ。急だったけれど、本当に楽しい旅行だったなと反芻しながら、仲謀に声をかけた。
「仲謀、お風呂は?」
「ああ、後で。ちょっと出かけるぞ」
「今から?」
「今からだよ」
予想外の言葉に首を傾げながらも、外は冷えるからと一枚余分に羽織らせられた。
手を引かれて外に出ると、昼間とは違って木々の茂りは暗く、怖くすらあった。お付きの者が数人ついてきているというが、姿は見えない。
生憎、三日月のせいで灯りも乏しい。足元を照らすのは仲謀が持っている提灯のみだ。
「……どこまで行くの?」
「もう少しだ」
梟か何かの声が森中に響き渡る。少し離れた場所でガサリと音が鳴ると、反射的に身体が震えてしまう。
「何だ、怖いのかよ」
「……当たり前だよ」
「俺様がいるんだから余計な心配すんな」
「…………」
単純なもので、そう言われた途端不安が薄れていくのがわかった。何だか悔しくて、返事の代わりに握った手に力を込める。先ほどまでは気が付かなかった夏の虫の鳴き声が、柔らかに辺りに反響する。そして少し坂を上り、樹木がない開けた場所に出た時のことだった。
「ほら、着いたぞ」
仲謀に導かれるまま辿り着いたその光景に、ただただ声を失った。
「―――――」
空いっぱい。真っ白とも言えるほどの星が散りばめられていた。すごく遠くにあるはずなのに、今にも星が落ちてきそうだ。星が瞬く度に音がしているような気さえする。ただそこに静かに存在しているだけなのに、圧倒的な光景は五感全てに訴えかけるようものを持っているようだ。
「すごいだろ」
「…………」
本当に、すごい。
住んでいた場所は元より、山に旅行へ出かけたことだってある。その時に綺麗な星空を見た気がしなくもないが、こんな星空は初めてだった。
「これを見せてやりたかったんだよ」
優しい仲謀の声に、また返事の代わりに手を握りしめた。何だか泣きそうで、唇を軽く噛みしめる。
「……ありがとう」
胸がいっぱいで、お礼を言うことしかできない。息苦しいほどの美しさに、しばらく溺れるように見入っていた。
身体が冷える前に帰ろう、と言われて、夢心地のまま手を引かれて歩き出す。
この世のものではないと思うぐらい、美しいものを見たからだろうか。タガが外れているのか、今なら言える気がした。
「……仲謀」
「なんだよ」
「……弟の話、していい?」
前を歩いている仲謀の顔は見えない。が、握った手に力が籠ったのがわかった。仲謀にとって聞きたい話なのかはわからない。それでも、言いたいと思った。
「……ああ」
「黄巾党の時代に飛んじゃった時のこと、覚えてる?」
「はあ?あ、ああ」
仲謀は思わぬ話題に面食らったようで、声が揺れる。
「仲謀と話しながらね、弟のこと思い出してた」
「……そうか」
「機嫌が悪くなると黙るとことか、弟みたいだなって」
「……お前、俺が年下なのを気にしてんの知ってて、それ言うか?」
「え、気にしてたの?」
「……もういい。で?」
疲れたような諦めた声音に促され、伝えたかったことを思い浮かべる。周囲は暗く、前を歩いているから仲謀の表情は見えない。見えなくて良かったと少し思う。暗がりが怖かった行きとは違う意味で、心臓がどきどきしている。
「……生意気な子なんだけど、年が離れてるから、あまり喧嘩とかはしたことなくて。わがままだし、どうせ私なら言うこと聞いてくれるだろう、って無理難題言うし。……でもね、姉ちゃんって頼られるの嬉しかった」
唐突に、涙が一粒だけ溢れた。
「大好きだった。大切で――」
たった一人の弟。
なのに、何故だろう。思い出そうとすると、酷く曖昧なことしか出てこない。もっと、弟がどんな子で、こういう良いところがあるんだとか、具体的に話そうと思っていたのに。仲謀に、知っていて欲しかった。私の大事な家族のことを――。なのに、一瞬一瞬を写真で切り取ったような表情が、ぱらぱらと浮かんでは消えていく。
どうやっても、これ以上弟について話すことが出来そうになかった。私は、弟に対する思い出も、言葉も、もうこれ以上持っていない。そして、それは母親と父親についても同じだろうと思った。
こうやって消えていくものなのだろうか。それとも、今まで話すことを避けていたから、忘れてしまったのだろうか。どちらにしろ、涙は最初の一粒しか流れなかったし、話すことが出来ない事実に対して、自分でも驚くほど悲しさは感じなかった。
急に、仲謀が立ち止まった。少し躊躇ったような間の後、振り返って少し驚いた顔をする。
「――泣いてんのかと思った」
涙の跡も残さなかった頬をゆっくりと撫でられた。その手を上からそっと握る。――何故悲しくないのか、わかった。
「……良かった」
「――何がだよ」
消えていく記憶が、仲謀ではなくて。
薄情だと思う。十七年過ごした場所、血の繋がった家族よりも、目の前にいる人の方が大事などと。帰らなかった後悔はまだ疼くけれど、苦しい時は仲謀がいれば治ってしまうことも知ってしまった。
今、私はこの人を忘れるぐらいなら、帰らなくて良かったと心から思ってしまった。
「……聞いてくれてありがとう。帰ろう」
釈然としないような仲謀の顔。いや、違う。不安そうな顔だ。ちゃんと言わなくてはいけない。
「私ね、ここに残って良かった。仲謀と、ずっと一緒に居たい」
他の何を捨ててでも、私は仲謀のことだけは諦められないんだ。
******
突然の休暇はあっという間に終わり、もう帰路に向かう馬車の中だ。風通し用に開けられた幕の隙間からは気持ちの良い風が入り込んでくるし、揺れは心地良いしで、欠伸が抑えられない。
仲謀はというと、ぼうっと外を眺めていた。
「お仕事はもう終わったの?」
「終わってねえ」
「……大丈夫なの?」
頑張りすぎていても心配だし、終わってないと聞くとそれはそれで心配だ。どことなく、いつもと様子が違う気もしていた。
「ま、少しくらい多めに見てくれるだろ」
仲謀は頭の後ろで腕を組んで、身体を伸ばした。今回の休暇を取るにあたり、相当無理をしたのだろうが、何故今だったのかを聞きそびれていた。
「都合が良いって言ってたけど……。何かきっかけでもあったの?」
「――別に」
頬杖をついて、じっと見つめられた。
「お前は……」
「?」
言い淀む仲謀に首を傾げる。
「楽しかったか?」
「うん。すごく楽しかった。連れて来てくれてありがとう」
「――そ、っか。またいつでも連れて来てやるよ」
「……うん」
いつでも。先の約束が出来ることが嬉しい。湧き上がる気持ちをそのまま伝えることが出来たらいいのに。
「また行きたい」
その言葉に、仲謀がやっと小さく笑った。途端、外で馬のいななきが響き渡る。何かあったのだろうか。そちらに気を取られていると、仲謀が小さく呟く声が聞こえた。
「? 何か言った?」
「いや、何でもねえ」
どこか吹っ切れたような表情で、笑いかけられる。
「仲謀様」
外からお付きの人が声をかけてきた。どうも先行していた馬車の車輪が道を外れてしまったらしく、対処中だという報告だった。
「ま、帰ったらまた仕事漬けだろうし、帰りぐらいゆっくりする」
「そうだね」
何を言っていたのか聞きそびれたことも忘れ、他愛のない話を再開する。
ようやく馬車も動き出し会話もなくなると、車輪が地面を踏みしめる音と、馬蹄が地面を蹴る音がやけに大きく聞こえた。外にいる兵士達が楽しそうに笑う声も。
周囲の音に耳を澄ませていると、本格的に睡魔が襲ってきた。
「寝とけ。まだしばらくかかる」
「……うん」
見ていないようで、花の様子は把握している。その安心感に、言われるまま素直に目を閉じた。
城に着くとすぐに大喬や小喬、尚香達が出迎えてくれた。離れていたのはほんの一日半だったというのに、何だかすごく久しぶりな気がする。お土産を渡して喜ぶ顔を見てから、仲謀は執務室へ直行し、花は休むために部屋へと向かった。あれだけ寝たというのに、いや寧ろ寝すぎたせいなのかまだ眠気が取れていなかった。
旅行は楽しかったものの、帰ってくるとそれはそれで安心する。それだけ、ここが自分にとって当たり前の場所になっているのだろうと思うと、嬉しかった。
そんなことを考えていると、廊下の向こうから公瑾がこちらへ歩いていくのが見えた。目が合う。
「――これは奥方様。お帰りなさいませ」
「た、ただいま帰りました……」
花の目下の課題は、公瑾とどう付き合うか……である。ここに至るまでに自分のことをよく思われていないのは明白だった。復帰してからは、少し物腰が柔らかくなったように思えなくもないが――。
「お祝いは楽しめましたか?」
「……お祝い?」
急に振られた話題に首を傾げる。何のことだろう。
答えられないでいると、公瑾が眉根を寄せた。
「――お祝いで行かれたのでしょう?」
「え、っと……?」
「…………」
沈黙が続いた後、公瑾が大きな溜息を吐いた。
「……奥方様」
「は、はい」
凛とした声で急に呼ばれ、背筋が伸びる。
「今の、聞かなかったことにして頂けますか?」
「へ?」
何を言われているのか飲み込めないでいると、公瑾が今まで見た中でも、とびきりの笑みを浮かべた。
「して頂けますか?」
「……はい」
彼は強めに私にお願いした後、袖で口元を隠しながら小さくぼやいた。
「――まったく、しょうがない人ですね」
何のことだろう。当然聞く勇気はなく、聞こえない振りをした。
「では、私はこれで」
「あ、はい」
ろくに会話も出来ないまま、いつも通りの涼し気な雰囲気で去っていく公瑾の背中を見る。
――お祝い?
聞かなかったことに、と言われて都合よく忘れられるわけがなく、歩きながら考える。
最近の出来事といえば、旅行しか思い当たることがない。旅行がお祝いだったということだろうか。何か祝うことなんて――。
たどり着いた答えに、思わず足が止まった。
――誕生日?
『色々あるんだよ。――天気も問題なかったし』
『これを見せてやりたかったんだよ』
『――別に』
仲謀の言葉が線を繋ぐように蘇り、胸が締め付けられた。何故、無理を通してでも出かけたのか。結局彼は理由を言わなかった。
肝心なことは、いつも言ってくれない。どんな気持ちであの場所に連れて行ってくれたんだろう。どうして、私ばかり楽にさせるのだろう。仲謀の、不安そうな顔を思い出した。
――寄りかかっているばかりだと、何も見えない。
「……ばかだなあ」
行き場のない感情が苦しいぐらい溢れて、衣の裾を掴んでやりきる。
さっきまでずっと一緒だったのに、どうしようもなく貴方に会いたい。
『夢幻の果て』 #仲花
webオンリー用に書きました。夏でしたので。
****************
細い、高い笛の音。あと、太鼓。ざわざわと人が話し、歩く音。屋台で売り買いする声。
目を開けると、真っ赤な鳥居があった。その向こうには眩しいほどの提灯や電灯が並び、写真や文字が各々の店の商品を宣伝をしている。甘い匂いはカステラだろうか。綿あめかもしれない。発電機特有の低い音があちこちから混ざって、祭りのお囃子の重低音を飾るかのように響いている。
「……お祭り?」
見覚えのある場所だ。見渡せば、近所の神社の境内であることがわかった。よく知っている、はずなのに。何故だかとても懐かしい。
人が往来するど真ん中に、私は突っ立っていた。どうしてここにいるんだろう。先ほどまで何をしていたのか、どうやってここまで来たのかも思い出せない。ふと何かを持っていることに気づき手元を見ると、巾着があった。と同時に浴衣の袖も目に入り、自分が浴衣を着ていることを知った。
とりあえず、歩くことにした。が、草履を履いていたため思わずつんのめってしまう。
「あっぶねえな」
誰かに腕を引かれ、前に倒れることは免れた。
「ぼうっとすんな」
「……仲、謀?」
そこに居たのは、よく見知った人物だった。なのに、違和感がある。
――ああ、そうか。
「浴衣着てきたんだ」
「……お前が着てこいって言ったんだろうが」
ふいっと背けた顔は、やや赤く色づいている。似合ってるよと声をかけると、うるせえと返された。そっか、いつもと違う服だから変な感じがしたんだ。段々と靄が晴れていくような心持ちで、仲謀に笑いかけた。
「私りんご飴が食べたいんだ」
「お前はいつも食い物のことばっかだな」
自然と手を繋いで歩き出す。が、やはり草履のせいで歩きにくい。人も多く、まっすぐ歩くのも困難だ。やっとの思いで目当てのりんご飴が並ぶ店まで来ると、種類も大きさも豊富でどれにするか迷ってしまう。
「前は苺にしてたぞ」
「そうだっけ?」
前っていつだろう。ぼんやり浮かんだ疑問。仲謀を仰ぎ見ると、「選べないからって二つも三つも食うと後で後悔するからな」と言われる。
「そんなこと考えてないよ」
「どうだか」
意地悪そうに笑う仲謀を軽く叩いて、色が一番綺麗な赤いりんご飴を選んだ。
「仲謀は何か食べたいのある?」
「見てから考える」
手を繋いで歩きながら、りんご飴を一口齧ってみる。途端、強烈な甘さにびっくりして、思わず足が止まってしまった。
「どうした」
「……何かこれ、すっごく甘い」
甘すぎる。はあ? と言いながら仲謀が私の手にあるりんご飴を齧った。
「別に。普通だろ」
甘党のくせに何言ってんだ、と言われ首を傾げる。普通? これが?
再び歩き出すも、りんご飴をもう一度齧ろうという気にはなれなかった。こんな甘すぎるもの、食べたら戻れなくなってしまいそうな気がする。
「射的があるぞ」
ぐいと手を引かれて転びそうになりながら、仲謀が進むままについていく。
「何か欲しいのあるか?」
「いや、特にはないけど――」
子どもではないのだから、お祭りの景品には興味がない。男の子ってこういうの好きだなあ、と少し離れた場所から見守ることにした。手に持ったままのりんご飴は、齧った部分が茶色く浸食し始めており、綺麗だと思って買った赤い飴の部分も毒々しい色に見えてくる。
ごみ箱があるのを見つけて、ごめんなさい、と心の中で断りながら捨てた。普段なら最後まで食べるけれど、今はどうしても食べる気にはなれなかった。
「あーくそっ」
戻ると、弾を打ち終えた仲謀が悪態をついている。
「当たらなかったの?」
「当たったけど倒れなかったんだよ」
次行こうぜ、とまた手を繋がれる。いつから、こんな風に仲謀と手を繋ぐのが当たり前になったんだろう。
「ねえ」
「あ?」
会場の奥の方は、人もまばらで歩きやすい。
「お祭りって、前もここに来たんだっけ?」
「そりゃそうだろ」
ここが一番近いんだから。そう言われて、殻が剥がれ落ちていくような奇妙な感覚を覚える。――近い?
「……仲謀の家って、どこだっけ」
「家? お前も来たことあるだろ」
全然、思い出せない。思い出せないけれど、仲謀の部屋を訪れたことはある。その逆も。ふと、祭り囃子の笛の音が耳に届く。そうだ、私の部屋で舞いの練習をした。笛や、色んな楽器を演奏してもらって――。
思わず、足が止まる。私の部屋って? 誰が私の部屋で演奏していたんだろう。
「どうした」
わからない。さっきから、何かおかしい。
「おい、顔色悪いぞ」
額に触れられた手は熱くて、仲謀が確かにそこにいる証のように思えた。心配して覗き込んでくる仲謀の瞳が、提灯と月明かりに照らされて青く見える。
「……帰るか?」
帰る――。どこに?
不安に駆られて、仲謀の手を握りしめた。
「い、っしょに?」
「お前一人で帰すわけないだろ」
呆れたように、でも安心させるように手を握り返された。
「お前が帰りたきゃ帰るし、まだいたいなら、それでもいい」
何故か、涙が零れた。何でこの人はこんなことを言うんだろう。『一人で帰さない』とは、私と一緒にいるということだ。私がここに残ると言ったら――。この人は大事なものを手放すというのだろうか。
「――決められないよ」
全部放棄してしまいたい。決めて欲しい。私に捨てる決意をさせないで欲しい。
「ここにいるか」
――一緒に。
付け加えられた言葉に首を大きく振った。決めて欲しいのに、結局私は自分で決めなければいけない。もう一度、この懐かしい場所に立ちながら、捨てなければいけない。――そうだった。私は仲謀と生きるために、この世界を捨てたんだ。
「仲謀、帰ろう」
そんな辛そうな顔をしないで欲しい。私は、何度故郷を捨ててでも、仲謀が大事なものごと傍にいたい。
ジーともリーとも聞こえる音が、遠くから聞こえる。もっと高い音もたまに混じる。――鈴虫だろうか。
目を開けると、窓の隙間から漏れる柔らかい月明かりが床を照らしていた。ぼうっとそれを眺める。しばらくしてから重い体をひねると、寝ている仲謀が目に入った。
さっきまで彼と話をしていた気がするのに、記憶を辿ってみても一緒に床に入った覚えがない。最近は忙しく、花が寝付いてからの帰宅が常になっていた。
見えない不安に駆られて、寝ている仲謀の手をそっと握りしめる。
――――。
「…………おやすみ、仲謀」
何か、違う言葉をかけたかったのに。今の自分はそれを持ち合わせていなくて、常套句を口にした。繋いだ手の温かさに安堵したのか、すぐに眠気が襲ってくる。瞼が重いのは眠いせいだと、自分の頬に残る涙の跡には気が付かないまま、再び深い眠りに落ちた。
webオンリー用に書きました。夏でしたので。
****************
細い、高い笛の音。あと、太鼓。ざわざわと人が話し、歩く音。屋台で売り買いする声。
目を開けると、真っ赤な鳥居があった。その向こうには眩しいほどの提灯や電灯が並び、写真や文字が各々の店の商品を宣伝をしている。甘い匂いはカステラだろうか。綿あめかもしれない。発電機特有の低い音があちこちから混ざって、祭りのお囃子の重低音を飾るかのように響いている。
「……お祭り?」
見覚えのある場所だ。見渡せば、近所の神社の境内であることがわかった。よく知っている、はずなのに。何故だかとても懐かしい。
人が往来するど真ん中に、私は突っ立っていた。どうしてここにいるんだろう。先ほどまで何をしていたのか、どうやってここまで来たのかも思い出せない。ふと何かを持っていることに気づき手元を見ると、巾着があった。と同時に浴衣の袖も目に入り、自分が浴衣を着ていることを知った。
とりあえず、歩くことにした。が、草履を履いていたため思わずつんのめってしまう。
「あっぶねえな」
誰かに腕を引かれ、前に倒れることは免れた。
「ぼうっとすんな」
「……仲、謀?」
そこに居たのは、よく見知った人物だった。なのに、違和感がある。
――ああ、そうか。
「浴衣着てきたんだ」
「……お前が着てこいって言ったんだろうが」
ふいっと背けた顔は、やや赤く色づいている。似合ってるよと声をかけると、うるせえと返された。そっか、いつもと違う服だから変な感じがしたんだ。段々と靄が晴れていくような心持ちで、仲謀に笑いかけた。
「私りんご飴が食べたいんだ」
「お前はいつも食い物のことばっかだな」
自然と手を繋いで歩き出す。が、やはり草履のせいで歩きにくい。人も多く、まっすぐ歩くのも困難だ。やっとの思いで目当てのりんご飴が並ぶ店まで来ると、種類も大きさも豊富でどれにするか迷ってしまう。
「前は苺にしてたぞ」
「そうだっけ?」
前っていつだろう。ぼんやり浮かんだ疑問。仲謀を仰ぎ見ると、「選べないからって二つも三つも食うと後で後悔するからな」と言われる。
「そんなこと考えてないよ」
「どうだか」
意地悪そうに笑う仲謀を軽く叩いて、色が一番綺麗な赤いりんご飴を選んだ。
「仲謀は何か食べたいのある?」
「見てから考える」
手を繋いで歩きながら、りんご飴を一口齧ってみる。途端、強烈な甘さにびっくりして、思わず足が止まってしまった。
「どうした」
「……何かこれ、すっごく甘い」
甘すぎる。はあ? と言いながら仲謀が私の手にあるりんご飴を齧った。
「別に。普通だろ」
甘党のくせに何言ってんだ、と言われ首を傾げる。普通? これが?
再び歩き出すも、りんご飴をもう一度齧ろうという気にはなれなかった。こんな甘すぎるもの、食べたら戻れなくなってしまいそうな気がする。
「射的があるぞ」
ぐいと手を引かれて転びそうになりながら、仲謀が進むままについていく。
「何か欲しいのあるか?」
「いや、特にはないけど――」
子どもではないのだから、お祭りの景品には興味がない。男の子ってこういうの好きだなあ、と少し離れた場所から見守ることにした。手に持ったままのりんご飴は、齧った部分が茶色く浸食し始めており、綺麗だと思って買った赤い飴の部分も毒々しい色に見えてくる。
ごみ箱があるのを見つけて、ごめんなさい、と心の中で断りながら捨てた。普段なら最後まで食べるけれど、今はどうしても食べる気にはなれなかった。
「あーくそっ」
戻ると、弾を打ち終えた仲謀が悪態をついている。
「当たらなかったの?」
「当たったけど倒れなかったんだよ」
次行こうぜ、とまた手を繋がれる。いつから、こんな風に仲謀と手を繋ぐのが当たり前になったんだろう。
「ねえ」
「あ?」
会場の奥の方は、人もまばらで歩きやすい。
「お祭りって、前もここに来たんだっけ?」
「そりゃそうだろ」
ここが一番近いんだから。そう言われて、殻が剥がれ落ちていくような奇妙な感覚を覚える。――近い?
「……仲謀の家って、どこだっけ」
「家? お前も来たことあるだろ」
全然、思い出せない。思い出せないけれど、仲謀の部屋を訪れたことはある。その逆も。ふと、祭り囃子の笛の音が耳に届く。そうだ、私の部屋で舞いの練習をした。笛や、色んな楽器を演奏してもらって――。
思わず、足が止まる。私の部屋って? 誰が私の部屋で演奏していたんだろう。
「どうした」
わからない。さっきから、何かおかしい。
「おい、顔色悪いぞ」
額に触れられた手は熱くて、仲謀が確かにそこにいる証のように思えた。心配して覗き込んでくる仲謀の瞳が、提灯と月明かりに照らされて青く見える。
「……帰るか?」
帰る――。どこに?
不安に駆られて、仲謀の手を握りしめた。
「い、っしょに?」
「お前一人で帰すわけないだろ」
呆れたように、でも安心させるように手を握り返された。
「お前が帰りたきゃ帰るし、まだいたいなら、それでもいい」
何故か、涙が零れた。何でこの人はこんなことを言うんだろう。『一人で帰さない』とは、私と一緒にいるということだ。私がここに残ると言ったら――。この人は大事なものを手放すというのだろうか。
「――決められないよ」
全部放棄してしまいたい。決めて欲しい。私に捨てる決意をさせないで欲しい。
「ここにいるか」
――一緒に。
付け加えられた言葉に首を大きく振った。決めて欲しいのに、結局私は自分で決めなければいけない。もう一度、この懐かしい場所に立ちながら、捨てなければいけない。――そうだった。私は仲謀と生きるために、この世界を捨てたんだ。
「仲謀、帰ろう」
そんな辛そうな顔をしないで欲しい。私は、何度故郷を捨ててでも、仲謀が大事なものごと傍にいたい。
ジーともリーとも聞こえる音が、遠くから聞こえる。もっと高い音もたまに混じる。――鈴虫だろうか。
目を開けると、窓の隙間から漏れる柔らかい月明かりが床を照らしていた。ぼうっとそれを眺める。しばらくしてから重い体をひねると、寝ている仲謀が目に入った。
さっきまで彼と話をしていた気がするのに、記憶を辿ってみても一緒に床に入った覚えがない。最近は忙しく、花が寝付いてからの帰宅が常になっていた。
見えない不安に駆られて、寝ている仲謀の手をそっと握りしめる。
――――。
「…………おやすみ、仲謀」
何か、違う言葉をかけたかったのに。今の自分はそれを持ち合わせていなくて、常套句を口にした。繋いだ手の温かさに安堵したのか、すぐに眠気が襲ってくる。瞼が重いのは眠いせいだと、自分の頬に残る涙の跡には気が付かないまま、再び深い眠りに落ちた。
『まだ見えぬ所有欲』 #仲花
合肥攻略(告白)前のおはなし。
****************
ほんの思いつきだった。――自分の部屋まで中庭を突っ切れば早いかも。早速階段を降り、生垣を抜けた瞬間――派手な衝撃音と共に、私は水を被っていた。
「……え?」
思考が追いつかず固まっていると、続いて上がった悲鳴にびくりと身体を震わせる。
「も、申し訳ありません!!」
使用人の女性が三人ほど、ばたばたと慌てて近寄ってきた。手には柄杓と桶。
「大丈夫でございますか? ああ、お召し物が濡れて――」
「すぐ着替えをお持ち致しますね。どうぞお部屋に」
どうやら生垣に水をやっているところに出くわしてしまったらしい。申し訳なさそうな彼女達に、近道しようとした自分が悪いのにと申し訳なくなる。
「大丈夫です。上着だけだし…。それより、私こそごめんなさ――」
「どうした!」
謝り終えない内に、悲鳴を聞きつけたのか仲謀とお付きの人たちが駆け寄ってきた。状況を一目見て、厳しい目つきになる。
「何があった」
強い咎めるような口調に、使用人達がさっと青ざめた。
「あの、違うの! 私がここを通り抜けようとしてたら、水遣りしてたのに気がつかなくて――!」
仲謀はちらりと私を一瞥し短く息を吐いた後、「早く替えを」と命令した。一人が慌ててその場を立ち去っていく。いつもと少し様子の違う彼に、ここの統治者であることを改めて実感していると、仲謀は側近に何かを指示してからこちらへやってきた。
「ほんっとにお前はガサツなやつだな!」
「う、……」
言いように少し腹が立つけれども、その通りで何も返せない。
「……で、大丈夫なのか」
「あ、……うん。ちょっと濡れただけだよ」
急に変わった気遣う声に、少し動揺する。服の状態を確認すると、羽織りはびしょびしょだった。中まで染みる前に、と脱いでみるとカーディガンまで濡れている。仕方がない、これも脱いでおこう、とボタンを外し始めると――、周りがどよめいた。
「なっ!にを、やってんだよ!」
「え?これも濡れちゃってて」
何故か慌てている仲謀に説明しながら脱いでみると、思ったより水を吸っていた。これは乾くのに時間がかかりそうだと考えていると、仲謀が「お前なぁ!」と怒り出した。
「これでも着てろ!」
言うが早いか、ばさりと仲謀の上着を被せられる。
「え、いや、いいよ……」
「嫌ってなんだ!」
「そ、そういう意味じゃなくて……」
ぐいぐいと無理やり上着を着せられながら、ふいに衣服から伝わる温もりに意図せず頬が熱くなる。――さっきまで仲謀が着てたから。
併せて過去に飛ばされた時にも、こうして上着を貸してもらったことを思い出してしまい、心が大きく波立った。――恥ずかしいんだけど。以前よりも大きく感じる羞恥心に戸惑っていると、じっと仲謀に見つめられていることに気が付いた。
「な、なに?」
「……別に。――チビだなと思っただけだ」
不機嫌そうに顔を背けられ、何か悪口まで言われた。――優しいかと思ったら怒りだす。相変わらず、仲謀の考えていることはよくわからない。
「……じゃあな。後で返せ」
「え、これ着てなきゃいけないの?」
この格好で部屋まで? 嫌だなという気持ちが思いっきり声に滲み出てしまった。
「――何か文句でもあんのか」
「……ないです」
青筋でも浮かびそうなほど凄む仲謀に、これ以上何か言えるはずもなく引き下がる。大股で歩いていく背中を見ながら、お礼も言わなかったことに今更気づいた。
彼が何を考えているのかは、わからないけれど。意外と優しいよね。意外と――。
自然と緩む頬に気づかず、侍女に連れられて部屋に戻る。そういえば、あの時は「一応女だから」と上着を貸してくれたのだった。そう、彼は意外と優しいから。
――私じゃなかったとしても、こうやって上着を貸したのかもしれない。
そう、思った途端。足元がぐらついたような感覚に足が止まる。使用人の一人が心配そうにかけてくれる声に、上の空で大丈夫ですと答えた。
何だか息苦しくて手を口元にやると、自分の物ではない、知らない匂い。
――何だろう、これ。
急に湧き出てきた名前の知らない感情を持て余して、無意識に上着の端をぎゅっと握りしめた。
合肥攻略(告白)前のおはなし。
****************
ほんの思いつきだった。――自分の部屋まで中庭を突っ切れば早いかも。早速階段を降り、生垣を抜けた瞬間――派手な衝撃音と共に、私は水を被っていた。
「……え?」
思考が追いつかず固まっていると、続いて上がった悲鳴にびくりと身体を震わせる。
「も、申し訳ありません!!」
使用人の女性が三人ほど、ばたばたと慌てて近寄ってきた。手には柄杓と桶。
「大丈夫でございますか? ああ、お召し物が濡れて――」
「すぐ着替えをお持ち致しますね。どうぞお部屋に」
どうやら生垣に水をやっているところに出くわしてしまったらしい。申し訳なさそうな彼女達に、近道しようとした自分が悪いのにと申し訳なくなる。
「大丈夫です。上着だけだし…。それより、私こそごめんなさ――」
「どうした!」
謝り終えない内に、悲鳴を聞きつけたのか仲謀とお付きの人たちが駆け寄ってきた。状況を一目見て、厳しい目つきになる。
「何があった」
強い咎めるような口調に、使用人達がさっと青ざめた。
「あの、違うの! 私がここを通り抜けようとしてたら、水遣りしてたのに気がつかなくて――!」
仲謀はちらりと私を一瞥し短く息を吐いた後、「早く替えを」と命令した。一人が慌ててその場を立ち去っていく。いつもと少し様子の違う彼に、ここの統治者であることを改めて実感していると、仲謀は側近に何かを指示してからこちらへやってきた。
「ほんっとにお前はガサツなやつだな!」
「う、……」
言いように少し腹が立つけれども、その通りで何も返せない。
「……で、大丈夫なのか」
「あ、……うん。ちょっと濡れただけだよ」
急に変わった気遣う声に、少し動揺する。服の状態を確認すると、羽織りはびしょびしょだった。中まで染みる前に、と脱いでみるとカーディガンまで濡れている。仕方がない、これも脱いでおこう、とボタンを外し始めると――、周りがどよめいた。
「なっ!にを、やってんだよ!」
「え?これも濡れちゃってて」
何故か慌てている仲謀に説明しながら脱いでみると、思ったより水を吸っていた。これは乾くのに時間がかかりそうだと考えていると、仲謀が「お前なぁ!」と怒り出した。
「これでも着てろ!」
言うが早いか、ばさりと仲謀の上着を被せられる。
「え、いや、いいよ……」
「嫌ってなんだ!」
「そ、そういう意味じゃなくて……」
ぐいぐいと無理やり上着を着せられながら、ふいに衣服から伝わる温もりに意図せず頬が熱くなる。――さっきまで仲謀が着てたから。
併せて過去に飛ばされた時にも、こうして上着を貸してもらったことを思い出してしまい、心が大きく波立った。――恥ずかしいんだけど。以前よりも大きく感じる羞恥心に戸惑っていると、じっと仲謀に見つめられていることに気が付いた。
「な、なに?」
「……別に。――チビだなと思っただけだ」
不機嫌そうに顔を背けられ、何か悪口まで言われた。――優しいかと思ったら怒りだす。相変わらず、仲謀の考えていることはよくわからない。
「……じゃあな。後で返せ」
「え、これ着てなきゃいけないの?」
この格好で部屋まで? 嫌だなという気持ちが思いっきり声に滲み出てしまった。
「――何か文句でもあんのか」
「……ないです」
青筋でも浮かびそうなほど凄む仲謀に、これ以上何か言えるはずもなく引き下がる。大股で歩いていく背中を見ながら、お礼も言わなかったことに今更気づいた。
彼が何を考えているのかは、わからないけれど。意外と優しいよね。意外と――。
自然と緩む頬に気づかず、侍女に連れられて部屋に戻る。そういえば、あの時は「一応女だから」と上着を貸してくれたのだった。そう、彼は意外と優しいから。
――私じゃなかったとしても、こうやって上着を貸したのかもしれない。
そう、思った途端。足元がぐらついたような感覚に足が止まる。使用人の一人が心配そうにかけてくれる声に、上の空で大丈夫ですと答えた。
何だか息苦しくて手を口元にやると、自分の物ではない、知らない匂い。
――何だろう、これ。
急に湧き出てきた名前の知らない感情を持て余して、無意識に上着の端をぎゅっと握りしめた。
『それは酩酊にも似た』 #仲花
エンド後で婚儀前のお話。
****************
「今から?」
「ああ、さっき決まった」
慌ただしそうに部屋に入ってきたかと思ったら、たった今から一週間留守にすると言われた。何でも地方の視察に行くらしい。婚儀まであと少し――。ただでさえ忙しそうにしているし、最近は会えない日も多くなっていた。
「……大丈夫なの? 体調とか」
「問題ない。というわけで、婚儀の準備の方はしばらく任せる」
「……それはいいけど」
「なんだよ?」
辛気臭い顔してんな、と軽く頬を引っ張られた。
「いっひゃいんだけど」
「ははっ。もしかして寂しいんだろ、お前」
「…………」
図星だ。というか、毎日顔を合わせられていない現状で、一週間も近くにいないというのに寂しくない方がおかしいのではないだろうか。
しょうがないやつだな、と何だかご機嫌そうな仲謀の顔を見ながら、ああ本当に行ってしまうのか、と足元が覚束ない気分になってくる。
「……後ろ向いて」
「はあ?」
「いいから。後ろ向いてよ」
なんだよ、と不審そうにしながらも、言う通り後ろを向いてくれる。そしてそのまま――、思いっきりぶつかるように抱き着いた。
「っ、のわ!」
何とか踏ん張ったらしい仲謀の背中に顔を押し付け、身体の前に回した腕でぎゅっとしがみ付く。寂しくて当たり前だという抗議と、離れる前にせめて――。と思ったのに、逆に仲謀の体温で泣きそうになってしまう。
「……花?」
「気を付けて。行ってきてね……」
今回は視察であっても、無事である保証はどこにもないのだ。身体の前に回した手に、仲謀の手が重ねられた。
「――何もないから心配すんな」
優しい声音に余計に切なくなりながら、仲謀の肩に顔を押し付ける。本当に、無事に帰ってこれますように――。
「……で」
「うん」
「何で俺は後ろを向かせられたんだ?」
「……恥ずかしいから」
「いや、正面からでいいだろ、普通に!」
「嫌だよ、無理」
「無理じゃないだろ、これじゃ何にもできないだろうが」
「……何もって、……何する気なの」
「おっ、前なあっ」
一旦離れろ、と重ねられていた手に力が込められた。
「やだよ、恥ずかしいじゃん!」
「今更なんだよ、馬鹿か」
引き剥がされないように必死にしがみついていると、バランスを崩して二人してその場に倒れこんだ。
「いっ、たぁ……」
思いっきり床に腰を打ち付けた。
「もう、仲謀のば――」
文句を言おうと前を見ると、思ったよりも近くに仲謀がいた。驚いて反射で逃げようとするも、腕を掴まれて逃げられない。
「え、ちょ」
「俺様から逃げられると思うなよ」
首の後ろに仲謀の手が滑り込んだ。首筋に触れた手の熱さに驚く暇もなく、口付けられた。
「~~~っ」
「で、俺様が何だって?」
してやったり、という顔で笑った仲謀の顔から目を逸らしながら、ばか、と呟いた。悔しい。打ち付けた腰の痛みも、床の冷たさも、全部忘れてしまうくらい仲謀のことでいっぱいにされるのだ。
「ちゃんと帰ってくるから、待っとけ」
「……うん」
再び近づく顔に、ゆっくりと目を閉じた。
エンド後で婚儀前のお話。
****************
「今から?」
「ああ、さっき決まった」
慌ただしそうに部屋に入ってきたかと思ったら、たった今から一週間留守にすると言われた。何でも地方の視察に行くらしい。婚儀まであと少し――。ただでさえ忙しそうにしているし、最近は会えない日も多くなっていた。
「……大丈夫なの? 体調とか」
「問題ない。というわけで、婚儀の準備の方はしばらく任せる」
「……それはいいけど」
「なんだよ?」
辛気臭い顔してんな、と軽く頬を引っ張られた。
「いっひゃいんだけど」
「ははっ。もしかして寂しいんだろ、お前」
「…………」
図星だ。というか、毎日顔を合わせられていない現状で、一週間も近くにいないというのに寂しくない方がおかしいのではないだろうか。
しょうがないやつだな、と何だかご機嫌そうな仲謀の顔を見ながら、ああ本当に行ってしまうのか、と足元が覚束ない気分になってくる。
「……後ろ向いて」
「はあ?」
「いいから。後ろ向いてよ」
なんだよ、と不審そうにしながらも、言う通り後ろを向いてくれる。そしてそのまま――、思いっきりぶつかるように抱き着いた。
「っ、のわ!」
何とか踏ん張ったらしい仲謀の背中に顔を押し付け、身体の前に回した腕でぎゅっとしがみ付く。寂しくて当たり前だという抗議と、離れる前にせめて――。と思ったのに、逆に仲謀の体温で泣きそうになってしまう。
「……花?」
「気を付けて。行ってきてね……」
今回は視察であっても、無事である保証はどこにもないのだ。身体の前に回した手に、仲謀の手が重ねられた。
「――何もないから心配すんな」
優しい声音に余計に切なくなりながら、仲謀の肩に顔を押し付ける。本当に、無事に帰ってこれますように――。
「……で」
「うん」
「何で俺は後ろを向かせられたんだ?」
「……恥ずかしいから」
「いや、正面からでいいだろ、普通に!」
「嫌だよ、無理」
「無理じゃないだろ、これじゃ何にもできないだろうが」
「……何もって、……何する気なの」
「おっ、前なあっ」
一旦離れろ、と重ねられていた手に力が込められた。
「やだよ、恥ずかしいじゃん!」
「今更なんだよ、馬鹿か」
引き剥がされないように必死にしがみついていると、バランスを崩して二人してその場に倒れこんだ。
「いっ、たぁ……」
思いっきり床に腰を打ち付けた。
「もう、仲謀のば――」
文句を言おうと前を見ると、思ったよりも近くに仲謀がいた。驚いて反射で逃げようとするも、腕を掴まれて逃げられない。
「え、ちょ」
「俺様から逃げられると思うなよ」
首の後ろに仲謀の手が滑り込んだ。首筋に触れた手の熱さに驚く暇もなく、口付けられた。
「~~~っ」
「で、俺様が何だって?」
してやったり、という顔で笑った仲謀の顔から目を逸らしながら、ばか、と呟いた。悔しい。打ち付けた腰の痛みも、床の冷たさも、全部忘れてしまうくらい仲謀のことでいっぱいにされるのだ。
「ちゃんと帰ってくるから、待っとけ」
「……うん」
再び近づく顔に、ゆっくりと目を閉じた。
『雨とこれから』 #仲花
夫婦後のお話です。『雨と嘘』と対になっています。
****************
――本当にどうしたというのか。
少し前までは、こんな風ではなかったと思う。暖簾に腕押しというか、こちらが好意を示してもせいぜい顔を赤らめるぐらいの反応しかしないし、返ってくる言葉は素っ気ないものだったり。
そもそも告白した時だって、はっきりと好きだと言われたわけではなく、やや強引であったことも自覚している。それがこの世界に花が残り、婚儀まで決まって。この辺りもまだ今ほどではなかった。
――今みたいに、花から触れてくることは。
夫婦になって、数か月。きっかけというきっかけは思いつかない。いつの間にか、少しずつ花の方から手を伸ばして、触れてくるようになった。
――お前、最近変だぞ。
いや駄目だ、これは悪手だ。まるで嫌みたいに聞こえる。
ああでもないこうでもないと考えこんでいると、仲謀、と名前を呼ばれた。
「好きだよ」
ぐっ、と息が詰まった。まただ。
こうやって触れてきた時は、大抵はっきりと好きだと告げてくる。――ていうか予定も詰まってる日中に、と頭を抱えたくなった。
「…知ってる」
違う。そうじゃねえ。
積極的にこられると、逆に身動きが取れなくなる。少し手を伸ばせば触れられた以前の方が、容易だったのに。大きな溜息をついて、天を仰ぎ見る。
――降参だ。
「…お前な、そんなに俺を煽って楽しいか」
まだ昼間だぞ、と言いながら花に抱きしめられている腕を少し解いて後ろを振り返る。が、背中にしがみつかれて顔が見えない。
「おい」
「だめ」
「あ?」
「今顔赤いから見ないで」
「…………」
――だから、何で昼間に。
怒りと何かに耐えながら苦し紛れに言い捨てた。
「…夜覚えとけよ」
「………」
花の腕にぐっと力が入った。
ざまあみろ、と思っていたのに。不意打ちを食らったのはこっちだった。
「……うん。待ってる」
――最近のこいつには本当に適わない。
息を吐きながら開け放たれたままの窓の外を見ると、雨足は和らいでいるようだった。遠くから、自分を探す声が聞こえてくる。もうそろそろ行かなければ。
「花」
雨の中、背中合わせに触れていた日が昨日のようでもあり、もう何年も昔のようにも感じられる。あんな風に何にも縛られずに過ごせる日は二度と訪れることはないだろう。孫呉を背負う自分には抱える物が多い。一緒にいることで自動的に背負わせてしまう花の重荷を取り除いてあげることもできないから。せめて伝えなければと思う。
「好きだ」
――ああ、二人きりの日々が二度と来ないなんてことはないか。
何年もこうして過ごして、世代が変われば。お前のことだけを考えられる時間が増える日がくるのだろう。だからそれまで――。
「傍に居ろ」
「――うん」
答えの後に、くすくすと笑い声が続く。
「急に変なの」
「…お前にだけは言われたくねえんだよ!」
探す声が更に近づいてきた。もう、時間だ。雨も止みそうだ。
「雨がね、降るたびに思い出すと思う」
何がとは言わない。でも、顔は見えないまま背中から伝わる声音で十分だった。
「そうだな」
こんな雨が降るたびに。きっと何度も何度も、思い出す。
夫婦後のお話です。『雨と嘘』と対になっています。
****************
――本当にどうしたというのか。
少し前までは、こんな風ではなかったと思う。暖簾に腕押しというか、こちらが好意を示してもせいぜい顔を赤らめるぐらいの反応しかしないし、返ってくる言葉は素っ気ないものだったり。
そもそも告白した時だって、はっきりと好きだと言われたわけではなく、やや強引であったことも自覚している。それがこの世界に花が残り、婚儀まで決まって。この辺りもまだ今ほどではなかった。
――今みたいに、花から触れてくることは。
夫婦になって、数か月。きっかけというきっかけは思いつかない。いつの間にか、少しずつ花の方から手を伸ばして、触れてくるようになった。
――お前、最近変だぞ。
いや駄目だ、これは悪手だ。まるで嫌みたいに聞こえる。
ああでもないこうでもないと考えこんでいると、仲謀、と名前を呼ばれた。
「好きだよ」
ぐっ、と息が詰まった。まただ。
こうやって触れてきた時は、大抵はっきりと好きだと告げてくる。――ていうか予定も詰まってる日中に、と頭を抱えたくなった。
「…知ってる」
違う。そうじゃねえ。
積極的にこられると、逆に身動きが取れなくなる。少し手を伸ばせば触れられた以前の方が、容易だったのに。大きな溜息をついて、天を仰ぎ見る。
――降参だ。
「…お前な、そんなに俺を煽って楽しいか」
まだ昼間だぞ、と言いながら花に抱きしめられている腕を少し解いて後ろを振り返る。が、背中にしがみつかれて顔が見えない。
「おい」
「だめ」
「あ?」
「今顔赤いから見ないで」
「…………」
――だから、何で昼間に。
怒りと何かに耐えながら苦し紛れに言い捨てた。
「…夜覚えとけよ」
「………」
花の腕にぐっと力が入った。
ざまあみろ、と思っていたのに。不意打ちを食らったのはこっちだった。
「……うん。待ってる」
――最近のこいつには本当に適わない。
息を吐きながら開け放たれたままの窓の外を見ると、雨足は和らいでいるようだった。遠くから、自分を探す声が聞こえてくる。もうそろそろ行かなければ。
「花」
雨の中、背中合わせに触れていた日が昨日のようでもあり、もう何年も昔のようにも感じられる。あんな風に何にも縛られずに過ごせる日は二度と訪れることはないだろう。孫呉を背負う自分には抱える物が多い。一緒にいることで自動的に背負わせてしまう花の重荷を取り除いてあげることもできないから。せめて伝えなければと思う。
「好きだ」
――ああ、二人きりの日々が二度と来ないなんてことはないか。
何年もこうして過ごして、世代が変われば。お前のことだけを考えられる時間が増える日がくるのだろう。だからそれまで――。
「傍に居ろ」
「――うん」
答えの後に、くすくすと笑い声が続く。
「急に変なの」
「…お前にだけは言われたくねえんだよ!」
探す声が更に近づいてきた。もう、時間だ。雨も止みそうだ。
「雨がね、降るたびに思い出すと思う」
何がとは言わない。でも、顔は見えないまま背中から伝わる声音で十分だった。
「そうだな」
こんな雨が降るたびに。きっと何度も何度も、思い出す。
『雨と嘘』 #仲花
夫婦後のお話です。
****************
ざあっと一際大きな音がして、思わず窓を開けて確認する。
「うわあ、すごい雨…」
長雨でしとしとと降る時もあれば、凄い勢いで雨が降り出すことがある。ふと、ぱしゃぱしゃと雨の中を走る影に気が付いた。
「――仲謀?」
慌てて布を手に取り外に出る。恐らく下にいるだろう、と慌てて階段を降りていくと、悪態をつきながら屋根の下に入ったばかりの仲謀がいた。
「仲謀、大丈夫?」
「…花」
驚いた様子の仲謀に駆け寄り、布を渡す。
「窓から見えたから。すごい雨だね」
「ああ。移動してたら降ってきやがった。この後も予定詰まってるのに…」
「早く着替えよう。風邪引いちゃうよ」
手を取ると思いのほか熱くて、まだ身体は冷えていないようだと安心する。仲謀はがしがしと頭を拭きながら回廊を通り階段を上った。
「着替え出すね」
「わりぃ。上だけでいい」
部屋に入ってすぐ替えを用意する。濡れた衣服を受け取りながら、まだ濡れている髪をじっと見つめた。
「ありがとな…ってなんだよ」
「…ううん」
「言えよ」
といっても大したことではないのだけれど。
「昔のこと思い出してた」
「昔?」
「あの時の雨も凄かったな、って」
「ああ、あれな。よく風邪引かなかったぜ」
少ない説明ですぐに思い出してくれたことに頬が緩みそうになる。こういう、小さなことが嬉しい。
仲謀を座らせ、濡れた髪を布でそっと拭いていく。柔らかい髪。その感触に昔のことを思い出して、仲謀の首筋をついっと撫でた。
「~~おっ、前な!」
「えへへ、ごめん。首弱いもんね」
「…お前、人のこと言えんのか?」
振り返って首筋を抑えたまま向けられた視線に、どきりとする。
「……言えるもん」
「どうだかな」
ふっと笑って仲謀が前に向き直る。ああ、どうしよう。息が苦しい。
ざあざあと降りしきる雨の音がやけに大きく聞こえる。
最近、息が苦しくなると仲謀に触れたくなる。なのに、昔と違って気持ちもすごく近くにあるのに、意識して触れようとするのはとても勇気がいる。
「花?」
急に黙り込んだのを訝しんで声をかけられる。
「おい、は、な――」
拭いていた手を止めて、後ろから抱きつく。濡れた髪が頬にすれてくすぐったい。――雨の匂いがする。
「……寒いかなと思って」
嘘。前と違って身体が冷えてないことだって知ってる。
昔なら、嘘なんかつかなくたって、容易に触れられたのに。今はすごく遠回りしないといけない。
仲謀の首の前で組んだ腕を掴まれた。
「…お前の方が冷えてんだろ」
戸惑いを含んだ声音に、この人のことが好きだなという実感がじわじわと湧いてくる。どんどん息が苦しくなる。治らない。
「どうした」
本当にどうしちゃったんだろう。二人だけで、雨の音と貴方の吐息以外音がしない場所で、息が苦しくても、体温を感じるだけでこんなに幸せ。
「仲謀」
どうしようもなく愛しくてしょうがない。
「好きだよ」
夫婦後のお話です。
****************
ざあっと一際大きな音がして、思わず窓を開けて確認する。
「うわあ、すごい雨…」
長雨でしとしとと降る時もあれば、凄い勢いで雨が降り出すことがある。ふと、ぱしゃぱしゃと雨の中を走る影に気が付いた。
「――仲謀?」
慌てて布を手に取り外に出る。恐らく下にいるだろう、と慌てて階段を降りていくと、悪態をつきながら屋根の下に入ったばかりの仲謀がいた。
「仲謀、大丈夫?」
「…花」
驚いた様子の仲謀に駆け寄り、布を渡す。
「窓から見えたから。すごい雨だね」
「ああ。移動してたら降ってきやがった。この後も予定詰まってるのに…」
「早く着替えよう。風邪引いちゃうよ」
手を取ると思いのほか熱くて、まだ身体は冷えていないようだと安心する。仲謀はがしがしと頭を拭きながら回廊を通り階段を上った。
「着替え出すね」
「わりぃ。上だけでいい」
部屋に入ってすぐ替えを用意する。濡れた衣服を受け取りながら、まだ濡れている髪をじっと見つめた。
「ありがとな…ってなんだよ」
「…ううん」
「言えよ」
といっても大したことではないのだけれど。
「昔のこと思い出してた」
「昔?」
「あの時の雨も凄かったな、って」
「ああ、あれな。よく風邪引かなかったぜ」
少ない説明ですぐに思い出してくれたことに頬が緩みそうになる。こういう、小さなことが嬉しい。
仲謀を座らせ、濡れた髪を布でそっと拭いていく。柔らかい髪。その感触に昔のことを思い出して、仲謀の首筋をついっと撫でた。
「~~おっ、前な!」
「えへへ、ごめん。首弱いもんね」
「…お前、人のこと言えんのか?」
振り返って首筋を抑えたまま向けられた視線に、どきりとする。
「……言えるもん」
「どうだかな」
ふっと笑って仲謀が前に向き直る。ああ、どうしよう。息が苦しい。
ざあざあと降りしきる雨の音がやけに大きく聞こえる。
最近、息が苦しくなると仲謀に触れたくなる。なのに、昔と違って気持ちもすごく近くにあるのに、意識して触れようとするのはとても勇気がいる。
「花?」
急に黙り込んだのを訝しんで声をかけられる。
「おい、は、な――」
拭いていた手を止めて、後ろから抱きつく。濡れた髪が頬にすれてくすぐったい。――雨の匂いがする。
「……寒いかなと思って」
嘘。前と違って身体が冷えてないことだって知ってる。
昔なら、嘘なんかつかなくたって、容易に触れられたのに。今はすごく遠回りしないといけない。
仲謀の首の前で組んだ腕を掴まれた。
「…お前の方が冷えてんだろ」
戸惑いを含んだ声音に、この人のことが好きだなという実感がじわじわと湧いてくる。どんどん息が苦しくなる。治らない。
「どうした」
本当にどうしちゃったんだろう。二人だけで、雨の音と貴方の吐息以外音がしない場所で、息が苦しくても、体温を感じるだけでこんなに幸せ。
「仲謀」
どうしようもなく愛しくてしょうがない。
「好きだよ」
『まどろみの中で』 #仲花
夫婦後のお話です。
****************
カタン、と小さな物音で目が覚めた。
うっすらと目を開けると、部屋の隅がぼんやりと明るい。
帰ってきたんだ。今、何時なんだろう。未だにくせで時刻を考えてしまう。
衣擦れの音がして、寝台が小さく軋んだ。
「悪い、起こしたか」
「⋯ううん」
寝台に入ってきた仲謀の手をそっと握ると、柔らかく握り返される。
「今日も忙しかったね」
「ああ。しばらくは仕方ねえな」
溜息をつきながら横になり、そのまま胸元に抱き寄せられた。
「朝も早いのにね」
「ああ」
欠伸をしながら頷くその声は、もう寝てしまいそうに揺らいでいる。
埋めた胸元で大きく息を吸うと墨の匂いがした。顔は見えないから、寂しさを隠すこ
とができる。
「お前は?」
「ん?」
「今日何してた?」
早く寝たらいいのに。
髪を漉き始めた手が泣きそうなほど優しくて、背中に回した手に力をこめる。
「楽しかったよ」
「だから何してたか聞いてんだよ」
「ひみつ」
「なんだそりゃ」
ふっと笑う声。顔は見えなくても、どんな表情なのかすぐに思い浮かべることができ
る。その顔が好きだから、直接見たいのにな、と思う。
「仲謀」
どんなに忙しくても、疲れていても、意識を手放す寸前まで大事に想ってくれている
ことを知っているから。
「おやすみ」
おやすみ、と言い合えた日は、寂しさが少し溶けていく。
夫婦後のお話です。
****************
カタン、と小さな物音で目が覚めた。
うっすらと目を開けると、部屋の隅がぼんやりと明るい。
帰ってきたんだ。今、何時なんだろう。未だにくせで時刻を考えてしまう。
衣擦れの音がして、寝台が小さく軋んだ。
「悪い、起こしたか」
「⋯ううん」
寝台に入ってきた仲謀の手をそっと握ると、柔らかく握り返される。
「今日も忙しかったね」
「ああ。しばらくは仕方ねえな」
溜息をつきながら横になり、そのまま胸元に抱き寄せられた。
「朝も早いのにね」
「ああ」
欠伸をしながら頷くその声は、もう寝てしまいそうに揺らいでいる。
埋めた胸元で大きく息を吸うと墨の匂いがした。顔は見えないから、寂しさを隠すこ
とができる。
「お前は?」
「ん?」
「今日何してた?」
早く寝たらいいのに。
髪を漉き始めた手が泣きそうなほど優しくて、背中に回した手に力をこめる。
「楽しかったよ」
「だから何してたか聞いてんだよ」
「ひみつ」
「なんだそりゃ」
ふっと笑う声。顔は見えなくても、どんな表情なのかすぐに思い浮かべることができ
る。その顔が好きだから、直接見たいのにな、と思う。
「仲謀」
どんなに忙しくても、疲れていても、意識を手放す寸前まで大事に想ってくれている
ことを知っているから。
「おやすみ」
おやすみ、と言い合えた日は、寂しさが少し溶けていく。
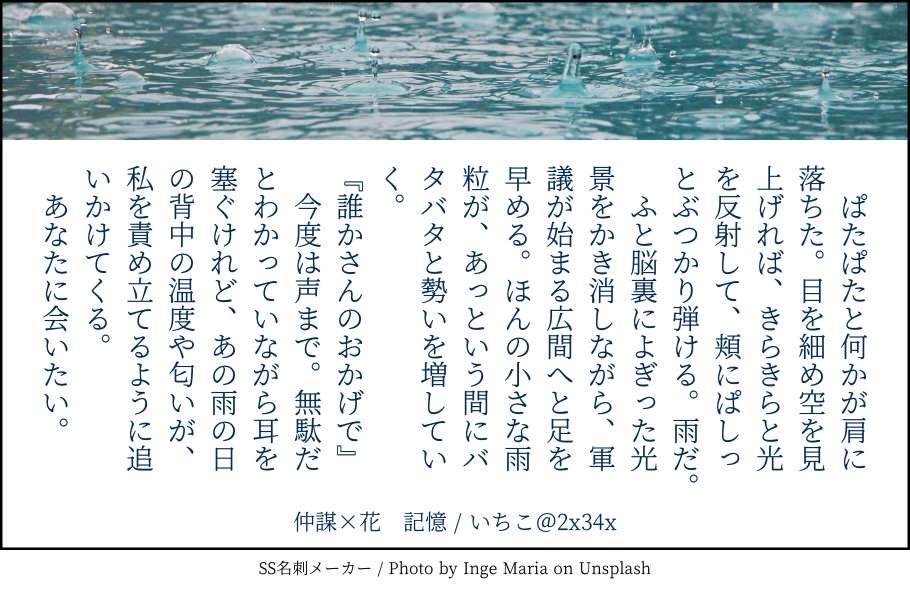
若干背後注意な内容ですが、あくまでも全年齢です。
「揉むと大きくなる」を仲花で……というフォロワさんからのネタをお借りして書きました。
****************
灯籠の油が焦げる匂い。芯が焼ける音すら聞こえそうな静寂だから、指先ひとつ動かすだけでも緊張してしまう。
殊更、布の擦れる音はやけに耳に残る――。
「……っ」
不意に漏れ聞こえた相手の吐息と、掌の中の違和感に、思わず身体が硬直する。続いてギッと寝台が立てた音に生唾を飲み込んだ。
「……仲謀?」
動きを止めた俺を訝しんで、腕の中にいる花が囁くような声で俺の名前を呼ぶ。
視界に入るのは花の後頭部だから、どんな顔をしているのかわからない。ただ、髪の隙間から見える耳の縁の赤さに気がついて、思わず目を逸らした。組み敷き見下ろしたときの、彼女の蒸気した頬と同じ色だから。
「……これ、本当に意味あんのか?」
脳内の彼女の姿に煽られ、理性を引き戻そうと言葉を絞り出す。
背中を俺に預けた花の体温と、柔らかな髪の香りだけでも限界だというのに。掌に沿って形を変える花の柔らかな胸の感触を、ただただ受け止めることしかできない。
何の拷問だろうか、これは。
飛びそうな思考を必死に留めるために、その原因をぼんやりと思い浮かべる。
『胸を大きくしたいから揉んでほしい』
余りにも唐突な話に面食らったのは、ついさっきのこと。言い終えた途端、顔を赤らめる花に何と返したかは覚えていない。
そんな話を聞いたことはなかったが、嫁にそんなことを頼まれて断る理由などない。花に触れるのだって初めてというわけでもないし、面と向かって言われたことが気恥ずかしいだけだ――。と、己が動揺していることも認められないまま手を伸ばそうとしたところで、極め付けの一言が放たれた。
『は、恥ずかしいから……。後ろからして』
思わず声を荒げそうになりながらも、背を向けた花に従ったが――。本当は、そこで押し倒してしまえば良かったのだろう。しかし、膠着こうちゃく状態にはまりこんだ今、後悔しても後の祭りでしかない。
お互いに呼吸すら憚はばかられるこの沈黙の中。じとりと伝わる熱は、もうどちらのものかもわからない。体勢を変えようと身じろぎしたところで、花が細く息を吐き、首をもたげた。
さらりと流れる髪の隙間から、白い頸うなじがのぞく。思わず、吸い寄せられるように唇を重ねようとして――。ぎりぎりのところで、額を擦り寄せた。
「……なに?」
骨身を伝わってきた花の振動する声に、大きく息を吐き切る。それくらいでは沸騰しそうな頭が静まるわけもなく、花の胸の膨らみから手を外し、後ろから拘束するように強く抱きしめた。
「……ねえ、まじめに」
「――してるっつの」
何が真面目に、だ。
どんな思いで触れているかも知らないで。お前だって乱れそうな呼吸を抑えているくせに。掌の中の柔らかな乳房は、布越しでもわかるほどにその形を変えようとしているというのに。
そのくせ、一人平気そうに装おうと取り繕うとするその姿が、とにかく気に食わなかった。
再び息を吐き、顔を上げる。自分だけこんなにも振り回されているのは不公平だろう――。
今度は、眼前の花の白い頸筋に意図的に唇を這わせ、そして舐め上げた。
「っ、なにっ」
花が身を硬くし、逃れようとその身を捩よじらせる。が、身体に回したままの腕を引き寄せてしまえば、何の意味もなさない。そのまま肌ごと吸い込むように強く強く口付けた。
「――っ」
花が、くの字に身体を曲げる。離していた手を再び花の胸に沿わせ、先ほどよりも力を込めて、でも傷つけないように加減して揉みしだいた。
「ちょ、っと! ちゅうぼ――」
相手の平静を突き崩せたことで、ほんの少し思考が晴れる。
そもそも――だ。
「ていうか」
細い花の肢体を横に寝台に向かって引き倒せば、いとも簡単に転がった。
乱れた夜着からはだけた、艶かしい肩に思わず息を呑みつつ、ここでまた振り回されてはならぬと唇を引き結ぶ。そして、何が起きたのか理解していないらしい、呆けた花の顔の横に手をついた。
「どんな体勢でやろうが同じだろうが」
やっと事態が飲み込めたらしい。さっと花の顔に走った朱に、溜飲が下がる。
恥ずかしいだとか何だとか知るか、と先ほどの花の言葉に脳内で返事をする。
一緒に乱れてもらわないと、話にならない。